
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
デイヴィッド・マレイ
撰者:大橋 郁
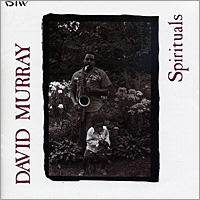
【Amazon のCD情報】
今回、私が大好きなテナーサックス奏者であるデイヴィッド・マレイのアルバム「スピリチュアルズ」を紹介したいと思い、所有しているマレイの他のアルバムを見ていてあることに気づいた。
「ラヴァーズ」「ディープ・リヴァー」「テナーズ」「スピリチュアルズ」は全て、1988年1月ニューヨーク録音であり、ミュージシャンは、デヴィッド・マレイ(ts)、デイブ・バレル(p)、フレッド・ホプキンス(b)、ラルフ・ピーターソン・ジュニア(ds)という固定メンバーで、レコーディングされている。(実は、私が所有していない「バラッズ」というアルバムも全く同じレコーディングデータなのだが)
あまり深く考えることもなく、これらのアルバムを聞いていたので気づかなかったが、調べてみると、要するにこれら5枚のアルバムは、1988年1月中の2週間近くを3回程に分けて、集中的にレコーディングした一連のセッションであったらしい。
この企画は、デヴィッド・マレイが当時レギュラーで活動を行っていたメンバーによってそのレパートリーの中から、バラッズやスピリチュアル、そしてテナーサックスの巨匠に捧げる曲などを録ろうということになり、上述のマラソンセッションを行ったというもの。
その中で、例えばバラッズばかり演奏を続けると堅苦しくなってしまうので、息詰まらないようにハードに吹きまくるナンバーも織り交ぜて、エンジョイしながら十分に時間を掛けて録り溜めしておき、アルバムとして編集する際に、内容によってカラーを分けて少しずつ発売していったようである。(発売は、88年、89年、90年、90年、93年)
さて、今回紹介する「スピリチュアルズ」は、この一連のセッションの中でも、タイトル通り、ブルースやゴスペルに根ざした曲調の作品を集めてある。全7曲のうち、3曲が黒人霊歌、残りはデイブ・バレル(p)のオリジナルが2曲と、マレイのオリジナルが2曲となっている。しかし、いずれにしても全てが黒人音楽のルーツに根ざした作品で統一されており、アルバムを特徴づけている。
デヴィッド・マレイについては、当コラム第42回で、松井さんが「ワールド・サキソフォン・カルテット(WSQ)」の傑作「リズム&ブルース」の紹介の中で、ロフト・ジャズ・ムーブメントに絡めて簡潔かつ明瞭に説明してくれている。【リンク】
1955年カリフォルニア生まれのマレイは、70年代半ばの20歳ころにニューヨークに進出してロフト・ジャズ・シーンで、頭角を表した。70年代のジャズ界は、フュージョン旋風が吹き荒れていたが、80年代はハービー・ハンコックのV.S.O.P.やら、ウィントン・マルサリスを筆頭とする新伝承派などが影響力を持ち、アコースティックにより戻された時代だった。しかし、そんな中でもマレイは、ロフト派という出自を持ち、毛色の違った流れの中に居た。
「スピリチュアルズ」は、1988年1月録音。マレイが33歳の時のものだ。そしてメンバーはこのアルバム録音当時、レギュラー的に活動していたメンバーであり、愛着を感じていたメンバーのようである。(因みに上述のWSQによる「リズム&ブルース」は同じ1988年の11月録音)
デヴィッド・マレイの演奏を聞いていて思うのは、恐らくこの人の頭の中には常に「アルバートアイラー」や「ニューオリンズ」そして「伝統」といったものがあったのではないだろうか、と勝手に想像している。
それくらい、私はデヴィッド・マレイを聞くたびに、アルバートアイラーとの親近性、賛美、敬愛を感じるのだが、それは決してフリージャズという括り方としてではない。確かにアルバートアイラーは、当時形骸化しようとしていたバップ形式に対するアンチテーゼもあったであろうが、ジャズという音楽が本来持つ大衆性、芸能性、祝祭性とでもいったような要素に回帰しようとしていたと思う。デヴィッド・マレイの演奏からは、それと似た空気を感じるのだ。確かにジャズ界はバップという偉大なジャンルを創造した。しかし、アイラーの時代、恐らく当時のジャズは自ら創造した偉大な形式が足かせになって前に進みあぐねていたのではないだろうか。
ジャズの成り立ちには、もちろん雑多な要素が複雑に絡まっている。ニューオリンズで成立したといっても、それだけではなく、例えばアイリッシュやユダヤ人の影響も大きいと思う。しかし、ニューオリンズという雑多な文化がぶつかり合う港町が、ジャズの成立に最も大きな影響を持ったことは事実である。松井さんが第18回と22回の当コラムで展開したアイラー論の中で「アイラーの音楽とチンドンの親和性に驚かされる。」と指摘しているように、ジャズという音楽は祝祭的要素を持つものなのだ。
話は少々逸れるが、ニューオリンズのお葬式は、ブラスバンドが賛美歌をおごそかに演奏しながら葬列の先頭に立って教会から墓地まで、しずしずと歩んでいく。しかし、一旦棺を埋葬してしまうと、一転して明るい曲を演奏して会葬者一同が楽しく踊りながら街中を練り歩く。これがセカンドラインだ。そのほうが死者の霊魂が安心して天国に行けるという考え方らしい。このような習わしや土壌から生まれた音楽であるジャズは、全ての大衆音楽がそうであるように、当然アブナさを抱えた音楽であったのだ。(残念ながら現在のジャズには、アブナさのない「お酒とセットで売る」「大人の音楽」的なものも多くなっている気がするが)
恐らくマレイは、心の中でアイラーと共に吹いていた。それくらいに精神的連帯性をもっていたのではないだろうか。このアルバムは全編を通して祈りを捧げるような演奏内容である。
1曲目の有名曲「アメイジング・グレイス」では、バスクラリネットを吹くが、正座をして聞きたくなる重厚さだ。続く2曲目の「デイブ・ブルー」は8分の6拍子のデイブのオリジナル・ワルツ。ブルージーに始まり、徐々にマレイが吠える。B面1曲目のゴスペル曲「誰も知らない私の悩み~ダウン・バイ・ザ・リバーサイド」では、ニューオリンズ・セカンド・ラインのリズムに乗って軽快に吹く。
また、このアルバムの最後の曲「アベルズ・ブリスト・アウト・ブルース」は、デイブ・バレル(p)のオリジナルで10分に及ぶ長尺曲であるが、冒頭はピアノによるスロー・ブルースで始まり、ちょうど中間時点で、突然アップテンポのゴスペル調に変わる。見事な展開である。全ての曲でマレイのソロは、始まると共に次第にフリーキーになり、高い音から低い音まで広い音域を、自在に行ったり来たりする。そして変化に富んだ音色を駆使して、めまぐるしくうねるフレーズが何処までも伸びていく。全く、この人のアタマの中はどうなっているのだろう、と思ってしまうくらい、自由なソロだ。高い音はフラジオという特殊な奏法を使っているらしい。
サックスの設計上、通常運指で出せる最高音はF#だが、これより高い音を、色んな穴の開き方の組み合わせと、喉、口、息をコントロールすることにより、無理やり出すのだそうだ。このように、マレイは実に技巧上も多彩な人である。
しかし、この人の志向はあくまでルーツであり、このアルバムはその面が強く出たアルバムだ。伝統とは、古いスタンダード曲を演奏することでもなければ、古い表現形式(演奏スタイル)に則って演奏することでもない。自分の中(あえて言うなら「血の中」)にあるもの、自然に胸に湧き上がるもの、それらに逆らわずに、自然にストレイトに表現することではないだろうか。
その意味では、この人ほど黒人音楽の伝統という自分の立ち位置をしっかり確認し、その流れの中に身を置いている、と感じる人はいない。私はこれからもマレイの音に浸り、そのウネリに包まれたいと思う。
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
