
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
イリノイ・ジャケ
撰者:吉田輝之
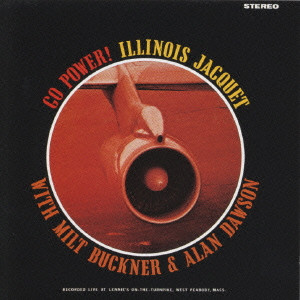
【Amazon のディスク情報】
こんにちは、9月の初め小雨の日々が続き少し切ない気持ちになり、お彼岸に入り秋晴れのなかでもっと切ない気持ちになっている吉田輝之です。
さて、そんな晴れた日に思いを馳せ、今週の一枚は「GO POWER/ILLINOIS JACQUET(イリノイ・ジャケ)」です。
※
『On A Clear Day(You Can See Forever)/晴れた日に永遠が見える』
1965年の同名ミュージカルの主題歌だ。作曲はバートン・レイン(Burton Lane)、作詞はアラン・ジェイ・ラーナー(Alan Jay Lerner)というミュージカルの黄金コンビだ。
1970年にバーブラ・ストライサンド、イブ・モンタン主役で映画化された。
Clear Dayだから本当は「澄んだ日」と訳すべきなのかもしれないが、「晴れた日」の方がこの曲にピッタリしている。
このミュージカルの主人公であるニューヨークに住む女学生デイジー(映画ではストライサンド)は花に触れると大きくしてしまう不思議な能力をもつ少女だ。彼女は精神病医学の講義でマルク博士(同イブ・モンタン)の催眠術にかかると前世の18世紀の公爵夫人メリンダという人格に戻ってしまう。デイジーには婚約者がいるのだが、マルク博士はデイジーというより前世のメリンダに激しく恋をしてしまう。ディジーは現在の自分でなく前世のメリンダに恋していることに失望して博士の電話をその超能力を使って無視するが・・・
という60年代のヒッピームーブメント(前世への降臨術、オカルト)を横糸に男女の行き違いを縦糸にした物語だが、ミュージカルとしては現在忘れられた存在ではないだろうか。
が、曲としては文字通り「永遠」の名曲スタンダードとして残った。
※
イリノイ・ジャケが1966年3月にマサチューセッツ州「レニーズ・オン・ザ・ターンバイク」でライブ収録したアルバム「GO POWER」はこの曲から始まる。ミュージカル公開の翌年の演奏だ。取り上げるのが実に早い。
他のメンバーはミルト・バックナー(オルガン)、アラン・ドーソン(ドラム)だ。
曲は遠くの方からドーソンのドラムが聞こえ、まるで記憶の奥底から沸きあがってくるかのようなバックナーのオルガンからイントロが始まり、ジャケが「On A Clear Day」とテーマの最初の一音を吹いた途端、聴く者は違う空間、時間に連れて行かれてしまう。
この演奏を聴くと僕は思うのだ。ジャケは“青春の尻尾"を引き摺りながら演奏をしていると。
〜〜〜〜〜
『ダイナ・ワシントンが友人たちとバーを出るとき、これからサヴォイ・ボールルームに行くところだというのを、私は小耳にはさんだ。そこではその夜ライオネル・ハンプトン楽団が演奏しており、彼女はその楽団で歌っていたのだ。
(略)ハンプトンの活気にみちた指揮は、アーネット・コブ、イリノイ・ジャケ、デクスター・ゴードン、アルヴィン・ヘイジー、ジョー・ニューマン、そしてジョージ・ジェンキンズといった偉大な楽団員たちと絶妙に息が合っていた。私はサイドラインから女の子を連れ出してフロアで二度ほど踊った。
サイドラインのブースの三分の一ぐらいは白人で占められていたと思うが、彼らの殆どは黒人の踊りを見学しているだけだった。だが中にはボストンと同じように黒人と踊る者もいて、数人の白人女性が黒人と踊っていた。
人々がハンプトンに『フライング・ホーム』をやってくれと叫んで、ついに彼は演奏した。
私はボストンでこの曲について聞いた話を信じていた。かってアポロ劇場で、マリファナを吸った一人の黒人がハンプトン楽団の『フライング・ホーム』を聞いていて本当に飛べると信じ込み、三階の桟敷席から飛び降り足を折ったという話である。その出来事はアール・ハインズが『セカンド・バルコニー・ジャンプ(三階の桟敷から飛ぶ)』というヒット曲を書いたことで歌にまで残る不朽のものとなった。)
こんな熱狂する踊りは見たことがなかった。』
(マルコムX自伝より)
〜〜〜〜〜
マルコムXの自伝にあるようにイリノイ・ジャケのテナーがソロをとったハンプトン楽団の「フライング・ホーム」は観客を熱狂の渦に巻き込んだ。
ハンプトンが初めて飛行機に乗る際に空港で待たされ苛立ち、その間吹いていた口笛の旋律がこの曲の元になっているという。
ハンプトン楽団がジャケにソロをとらせて最初に録音したのが1941年だ。
ちなみに、ジャケがハンプトン楽団に入ったのはナット・キング・コールの紹介だという。
【閑話休題】
以前、大橋さんが紹介されたハンプトンの「All Star Band at Newport‘78 」での「フライング・ホーム」を元町のジャズバーDoodlinで聴いていると、マスターのチャチャイさんが言うに「この曲はどこまでがテーマでどこまでがアドリブなんでしょうか。わからないですね。それに(どのサックス吹きも)みんな同じように吹いてますね」と。そうです、この曲、ジャケの演奏はアドリブと編曲が一体になっていてアドリブ部分も含め曲になっているのです。そのため後任のアーネット・コブを初めみんなジャケと同じように演奏しているのです。
それでは本文に戻ります。
※
この曲を聴いた客が3階から飛び降りたというエピソードは僕がジャズを聴き始めた70年代初頭には既に「伝説」になっており、FMのジャズ番組でハンプトンの曲がかかる際に必ず引用された。ただ、それはジャケが乗りに乗って演奏し観客も興奮の余り行き過ぎてしまったという「微笑ましい」話として語られていたと思う。
しかし1941年、ジャケがフライング・ホームを演奏したことはポピュラー音楽史上、極めて大きな事件であった。何故ならここからR&Bの歴史が始まり(もしくは顕在化して)、後のロックン・ロールへの扉が開いたのだ。このことは大橋さんの【第65回】のハンプトンのコラムを参照していただきたい。
ジャケは1922年生まれでフライング・ホームを最初に演奏したのは何と19歳の時だ。
1922年生まれというのはかなり意外に感じる。影響を受けたベン・ウエブスター、レスター・ヤング(ともに1909年生)より少し後の生まれではないかと漠然とした印象を僕は持っていたのだが、実際は彼らより一回り以上若いのだ。
〜〜〜〜〜
「カンザスシティでのある夏の夕方、私が演奏(アルト)する姿を一人の男が見つめていた。演奏が終わるとその男は私を呼びとめた。
(その男もアルト吹きで),その後、二人で別のクラブに行き演奏(jamming)を始めた。私と彼の演奏スタイルは極めて似ていた。私は思った、彼が演奏するとそれはまるで私(が演奏しているよう)だった。(Our styles were so much alike that when he would play、I thought it was me)」
〜〜〜〜〜
「私」というのはイリノイ・ジャケであり「彼」というのはチャーリー・パーカーだ。
二人がカンザスシティにいた1930年代の後半のある夏の晩の「邂逅」をジャケは1988年のJAZZ TIMESのインタビューで懐かしそうに語った。共に10代のときだ。ジャケはハンプトン楽団に入るまではアルトを吹いていたのだ。
ジャケは1920年生まれのチャーリー・パーカーと同世代人であるに留まらず、10代においてジャケはパーカーでありパーカーはジャケであるという音楽上の「双子」「対(ツイ)」だったのだ。
ジャケの吹くフライング・ホームが爆発的な人気を博した1942年に無名のパーカーはニューヨークにやってくる。そこでパーカーはビー・バップという革命を起こした。
【閑話休題】
違うよ、クリント・イーストウッドさん。あなたは素晴らしい俳優で監督だけど間違っているよ。あなたが監督した「バード」の(確か最後の場面)で刑務所(療養所?)から久しぶりに出て来たパーカーが世間ではR&B一色になっており呆然とするというのは間違っているよ。
パーカーはそんなことで驚くような「タマ」ではないよ。
※
極論すればR&Bとビー・バップはジャケとパーカーという音楽上の双生児によって同時に生み出された。R&Bとビー・バップは1930年代まで世界的にみてローカルな存在であった新興国アメリカの黒人音楽を戦後、世界音楽に飛躍させることとなった二大音楽革命だ。
パーカーとジャケ、この同じ根を持つ二人は「天才児」という言葉では括りきれないほどの「破格の人」であった。
この二人こそプロメーテウスのごとく20世紀のポピュラーミュージックに「火」をもたらした「文化英雄(Culture Hero)」なのだ。
パーカーの演奏を聴いた者は
「何をやっているかまるでわからないが、何てすごいんだ」と驚き、
ジャケの演奏を聴いた者は
「何をやっているかものすごくわかるが、何てすごいんだ」と驚いた。
ジャケはハンプトンの楽団を皮切りに1941年から43年までキャブ・キャロウエイ楽団に移り、43年から44年までJATPで観客を熱狂させるがダウンビート誌で悪評を買い、44年からカウント・ベイシー楽団に入りベイシーから「うちのTHE END(切札)」と呼ばれただけではなく、40年代前半に「鋼鉄の喉」を持つ男ワイノリー・ハリスとポピュラー音楽史上最強のタッグを組み、さらには兄ラッセル・ジャケ(トランペット)、レオ・パーカー(バリトン)と北米大陸を暴れまくった。もう40年代のジャケは無敵です。
ジャケはR&Bやブルーズのサックス奏者にも絶大な影響を与えたが、その生涯を見れば一生「ジャズ」の人だった。彼は50年代以降も「ある種の大スター」として2004年81歳までほぼ現役として生きながらえた。93年にはクリントン大統領が「長年の憧れの人」としてジャケと共演したぐらいだ。
60年代以降のレコーディングを見ても、松井さんが紹介されたハード・バップセッションの他に、ボサノバアルバムやウイズストリングスもの、メッセージアルバム、ビッグバンドなど実に多彩だ。
しかし「素(ス)」のジャケを捉えたレコードとしては何といっても「GO POWER(1966年/CADET)」に止めをさす。ミルト・バックナー、アラン・ドーソンというハンプトン楽団ゆかりの3人編成のこのアルバムにはジャケの全てが凝縮されている。
※
それにしても「GO POWER」、何と「漢(オノコ)」の心を打ち震わすタイトルであろうか。
これはやはり「豪力(ゴウリキ)」と意訳したい。
1969年にもやはりミルト・バックナーが入った11人編成の「THE SOUL EXPLOSION」という傑作があるが、こちらはさしずめ「魂爆(タマバク)」若しくは「爆魂(バクタマ)」とでも訳すべきか。
ジャケット写真のジェット機の噴射口は、おそらくテナーサックスの朝顔管(ベル)を象徴しており「俺のテナーのパワーはこんなにすごいんだ」とでも言っているかのようだ。
しかしあえて言えば、このレコードの魅力は一般的な「ゴリゴリ」という意味でのパワーがあふれているということだけではない。確かにこのライブ演奏での「ILLINOIS JACQUETS FLIES AGAIN(=フライング・ホーム)」や「WATERMELON MAN」というアップテンポナンバーでのパワーは凄い(ミルト・バックナー最高!)。このレコードが「コテコテのジャケの代表作」と言われている理由はよくわかるのだ。
しかしながら本当に重要なことは、このレコードからあふれ出てくるジャケが持つ空間と時間をウィザードなものに変える力だ。
「ROBBIN'S NEST」「I WANT A LITTLE GIRL」「PAMELA'S BLUES」「JAN」などのナンバーはバックナーのオルガン演奏との相乗効果でジャケの「豪放磊落」なイメージとは明らかに異なる幻想的なイメージが横溢している。
そして何より冒頭の「ON A CLEAR DAY」だ。
この演奏時、ジャケは44歳。この演奏にはどこか若き日の青春の火照りを感じさせ聴く者を過去に連れ戻してしまう。
この曲を聴き昔日の日々を思い出したら外に出よう。
「ある晴れた日に、顔を上げて見回してごらん、きっと本当の自分がわかるから。」
1. ON A CLEAR DAY
2. ILLINOIS JACQUET FLIES AGAIN
3. ROBBIN'S NEST
4. WATERMELON MAN
5. I WANT A LITTLE GIRL
6. PAMELA'S BLUES
7. JAN
※
【 蛇足たる補足 1 】
僕は90年代になるまでジャケがどのような存在であるかよくわかっていませんでした。
松井さんが【第58回】のコラムで述べられているようにジャケは元祖「ホンカー」と言われています。ジャケはベン・ウエブスターからグロウル(声と音を同時に出す)を、レスター・ヤングから多彩なフレージングを学び、さらにホンキング(ヴァーヴァ・ヴァブといったリフ)、スクリーム、ホーシング(馬のいななきのような叫び声)といった後のホンカー達が使う技術の殆どを彼が確立しました。その演奏技法はサックスを発明したアドルフ・サックス氏がもし聴いたら激怒したことでしょう。
しかし本文にあるようにジャケはR&Bの扉を開きましたが、ジャズのフィールドで一貫して活動をしてきました。僕もSIL AUSTINのコラムを書いてから改めてホンカーについて調べましたが、ホンカー(HONKER)という言葉は欧米ではかなり限定的に使われており、むしろJAZZもBLUESもR&Bも含め「ブローテナー(BLOW TENOR)」と言う方が一般的なようです。
以前のこのコラムで僕は、「ホンカーとは本質的にジャズマンと言うよりブルーズマン、芸術の徒というより芸能の輩(やから)」と書きました。
ジャケはホンカーたる全ての条件を提示しましたが、実はホンカーというイメージをはるかに逸脱した存在です。
ジャケは元祖「武闘派」、いやキーを打ち間違えました、元祖「ブロー派テナー」なのですね。
【 蛇足たる補足 2 】
ジャケの代表作といえば「FLYING HOME」そして「ROBBIN'S NEST」ですね。この「ロビンズネスト」、村上春樹さんの「国境の南、太陽の西」で主人公が営むジャズクラブの名前でハルキファンにも広く知られておりますが、ジャケとサー・チャールズ・トンプソンが作曲した曲です。確かもともとロビンさんというDJのラジオ番組のテーマ曲で、DJの名前と「小鳥の巣」を引っ掛けているのですね。非常に不思議なムードを持った曲です。
【 蛇足たる補足 3 】
ジャケという人、松井さんのコラムでも書かれていましたが、両親がクレオールでさらにインディアンの血も流れているという複雑なルーツを持つ人です。つまりヨーロッパ大陸、アフリカ大陸、ネイティブなアメリカ大陸、さらにはインディアンのルーツというべきアジア大陸の血を引く「稀人(まれびと)」でした。
ジャケは自分の事をはたして「黒人」と認識していたのでしょうか。前世、現世、来世を通じて「自分は自分」と感じていたのではないでしょうか。『On A Clear Day(You Can See Forever)/晴れた日に永遠が見える』という摩訶不思議なミュージカルの内容に引っ掛けてそのことを書こうと思い、この文章を書き始めたのですが、うまく書けないのでその部分は大幅にカットしました。
【 蛇足たる補足 4 】
ミルト・バックナー、この人も不思議な人です。短躯で牛乳瓶眼鏡の異相の持ち主、人種がまるでわかりません。このレコードのグルーヴを決定づけているのはバックナーのオルガンなのですが、奏法が他のオルガニストと全然違います。継承者はジミー・マクグリフぐらいでしょうか。興味が尽きません。
【 蛇足たる補足 5 】
パーカーとジャケ、この二人についてはJATPに一時一緒にいたぐらいで、二人の関係について述べた文章(ジャズヒストリー)を今まで読んだことがありません。だいたい日本のジャズファン(に限らないのかもしれませんが)でパーカーを聴く人はジャケを聴かず、ジャケを聴く人はパーカーを聞かず、お互いが全くの関心外なのです。
しかし、以前ネットでジャケのインタビューを読み、本文にあるようにアルト時代のジャケの演奏スタイルは偶然にもパーカーと全く同じだったと知り、正直全身に電流が走りました。
【 蛇足たる補足 6 】
この「GO POWER」というアルバム、ジャケの「コテコテレコード」の代表作として(一部の人に)有名で僕もそう思ってきましたが、この一ヶ月毎日聴き、かなり印象が変わりました。そのためレコードのコメントがギクシャクしており、まことにすいません。
しかし、わずか4歳違いのコルトレーンが「至上の愛」から「アセッション」に向かう1966年に、ジャケは何というレコードを作ってしまったのでしょうか。そのことを考えただけで頭がくらくらしてしまいます。
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
