
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
ライブ・アット・ザ・ハーレム・スクエア・クラブ1963
サム・クック
撰者:吉田輝之
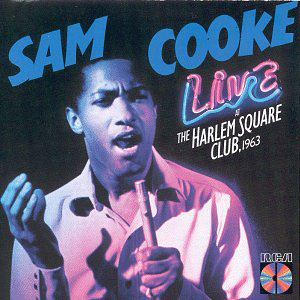
【Amazon のディスク情報】
こんにちは、7月の猛暑の土曜日、昨年に続きエアコンが故障してショックを隠しきれない吉田輝之です。しかしワタクシ、人様から意外に思われるのですが、実は・・・夏はすごく暑い方が好きです。
さて、今回は「ゴスペル(セイクリッド・ミュージック)と世俗音楽(セキュラー・ミュージック)」の3回目です。
レコードは、またまたまたジャズではなく、とりあえず「HARLEM SQUARE CLUB 1963/SAM COOKE」です。
※※
サム・クックというひと、現在ではレイ・チャールズ、アレサ・フランクリン、オーティス・レディングと並びソウルミュージックのパイオニア、偉大な黒人歌手して世界的に認識されている。黒人音楽ファンに止まらず、音楽ファン一般にとっても「神格化」された存在とさえいえる。
しかし、1970年代半ばぐらいまでは、サム・クックは一般的に「ソウル」歌手としてのイメージは殆どなく、むしろ「ポピュラー」歌手として認識されていた。この場合の「ソウル」というのは「黒人的」と言い換えてもよい。AMラジオでかかる彼の曲はハーマンズ・ハーミットがカバーした「WONDERFUL WORLD」や「CUPID」といったポップな曲が圧倒的に多く、僕もそういう歌手と認識していた。
しかし10歳代の半ば頃から黒人音楽を聴きだし、一般の音楽雑誌では飽き足らず「THE BLUES」「SOUL ON」「SOUL TO SOUL」などの専門誌やファンジンで情報をあさっていると、
「実はサム・クックは、凄くディープな歌手だ。」
「黒人歌手でゴスペル出身者は星の数ほどいるが、ゴスペルと世俗音楽ともに超一流の人気を得たのはサム・クックだけだ。」
「サザンソウル歌手の殆どがサム・クックの影響を受けている。」
と書かれているではないか。
ただ、街の一般のレコード店でそのことを確認できるレコードは、当時売っていなかった。
前回ふれた通り70年代の後半になってゴスペルのレコードが一部の輸入盤店に出回り、僕もサム・クックがリードを務めたSPECIALTY時代のソウル・スタラーズ(SOUL STIRRERS)を聴いてようやくサム・クックの「DEEP」サイドを知ることができたのだ。
しかしゴスペル時代のサム・クックを聴いていたのは一部の黒人音楽ファンだけであり、一般的に彼の評価が一変したのは、何と言っても1985年にリリースされた「HARLEM SQUARE CLUB 1963」の、「衝撃」による。このレコードのリリースはアメリカポピュラー音楽史上の「事件」とさえ言える。ゴスペル時代のサム・クックを知っているマニアの多くもこのレコードを聴きひっくり返ったはずだ。
このレコードは標題通りマイアミの黒人街にあるクラブ「ハーレム・スクエア」での1963年のライブ盤だ。ここでのサム・クックはRCAでのヒット曲とはまるで違う。激しくシャウトし、その声は途轍もなく生々しく、荒荒しくも完璧だ。キング・カーティスのバンドもバックに徹しながらも実にダイナミック。観客も熱狂している。このレコードは、聴く者全てを時と空間を超えて1963年1月のハーレム・スクエアに連れて行き、観客の一人にして熱狂させてしまう凄いレコードだ。
このレコード聴き感激した僕は、翌1964年に録音したもう一つのLIVEアルバムである「AT THE COPA」もどうしても聴きたくなり、探し出して聴いたが、ハーレム・スクエアとは対照的なポピュラーミュージック然として唄い方、ビッグバンドのバック、観客の行儀良さに正直拍子抜けしてしまった。
これは僕だけではないと思うが、ハーレム・スクエアを聴いた多くの人は、ハーレム・スクエアでのサム・クックこそが「本当」のサム・クックであり、コパやスタジオ録音されたRCAのヒット曲でのサム・クックは「仮」、若しくは「偽り」のサム・クックであると思い込んでしまったはずだ。
しかし、僕はハーレム・スクエアが出た翌86年に出された、ゴスペル時代からRCAのヒット曲まで網羅した「THE MAN AND HIS MUSIC」というコンピレーションを聴いて、ハーレム・スクエアが「本当のサム・クック」とは言えないと思うようになった。少しバカにしていたRCA時代のヒット曲も実にいいのだ。特に「YOU SEND ME」の軽く自然で、しかも深みのある唄い方なんて誰にもまねができない。しかも驚くことに、これらにヒット曲の殆どはサム・クックのライティングなのだ。
ティーンエイジャー向けのポップソングを唄って、ここまでの深さと高みに達した歌手は唯一サム・クックだけだろう。
サム・クックは20世紀の「時代精神(ツァイガイスト)」とアメリカ黒人の「民族の魂」が産み出した紛れもない天才歌手だった。
けっこう怒りっぽい人だったらしいが、こと「歌」に関しては「我(が)」が驚くほどない。
RCAというカントリー・アンド・ウエスタンで基盤を固めた大レーベルと契約を結び、白人層に売るがための意図的な戦略はあっただろうが、クックは何より本能的にその時々の聴衆が何を望んでいるかを瞬時に感じ取り、求められるものを無制限に与えることが出来た稀有な表現者だった。ハーレム・スクエアの黒人聴衆にもコパの白人聴衆にも夫々が求めるものを与えたにすぎず、どちらが本当のサム・クックということはありえないのだ。
さらにサム・クックは「歌手」と言う枠をはるかに超えて、ヴィジョン、パッション、ミッションの全てを持ち、「聴衆」を「民衆」まで拡大して影響力を持ち得たであろうカリスマだった。
もしサム・クックが1964年に謎の死をとげなかったら、アメリカ初の黒人大統領誕生は20年以上早まっただろう。
※
いやぁ、もうサム・クックのことになると話にキリがなくなるので、本論に戻しましょう。
僕は10歳代の半ばからゴスペ音楽を聴きだしたことは前回に書いた通りだ。当然、ゴスペルというのは「黒人のキリスト教音楽」だと思っていた。しかし、内容もわからず、ジャケットに「GOSPEL」と書かれたレコードを片端から買っていると、たまに白人がカントリースタイルで歌っているゴスペルレコードがあり、聴いてかなり面喰らった。それで、はじめて白人の唄うキリスト教音楽もゴスペル(WHITE GOSPEL)と言われていることを知った。
一方当時、黒人のゴスペルカルテットのマイティ・クラウズ・ジョイが当時のフィリーソウルに近いサウンドのゴスペルレコードを出してかなりの話題となっていた。
もともとアメリカのゴスペルという宗教音楽は、世俗音楽の影響を歴史的に強く受けてきた音楽なのだ。
つまり、人種やその楽曲のスタイルに関係なく歌詞のテーマが「キリスト教」に関係するならそれは「ゴスペル(宗教)音楽」であり、それ以外の例えば男女間の事柄をテーマにしていれば「セキュラー(世俗)音楽」と呼ばれているのだ。このことは当たり前と言えば当たり前のことだ。
この定義に従えば、ハーレム・スクエアであれコパであれ「世俗音楽」に他ならない。正確に言うとハーレム・スクエアは「明らかにゴスペル唱法で唄った世俗音楽」、コパは「あまりゴスペル唱法を出さずに唄った世俗音楽」ということになるだろう。
しかし、僕は、ハーレム・スクエアでのサム・クックの音楽は「本質的にゴスペルそのもの」と直観した。それは前回述べたオーティス・クレイのLIVEについても全く同じだ。
ただ、その「ゴスペルの本質」とは何かといえば、まるでわからなかったのだ。当時から「ハーレム・スクエアはゴスペルだ」と断言する評論家やファンが多かったと思う。ただその根拠がサム・クックのゴスペル唱法だけに準拠しており「それだけなのかな」と僕は釈然としなかった。
確かに、サム・クックにしろ、前回ふれたオーティス・クレイにしろ、その歌手としてのゴスペル唱法には圧倒された。しかし、レコードを何回も聞いて反芻しているうちに、我々を狂喜させた源泉はゴスペル唱法を含むライヴでの「ドラマツルギー」(劇的な筋書きと演出)にあると確信するようになった。
実際に経験したオーティス・クレイのLIVEを例にとると、超スローの「I CAN'T TAKE IT」でクレイは跪き、マイクを使わずに唄声を会場に響き渡らせ、我々を圧倒し感情を深い井戸に落とし込ませる。そして次にミディアムテンポの「SLOW AND EASY」で明るい気持ちに持ち上げたと思いきや、続く自分の想いが届かぬ苦しい思いを訴える「IS IT OVER」「THAT''S HOW IT IS」で聴衆の感情を再び深く底の底に落とし込んだ直後、<間髪を入れず>に「TURN BACK HANDS OF TIME」「TRYING LIVE MY LIFE WITHOUT YOU」へと怒濤のごとくなだれこみ我々を爆発、解放させてしまった。
前回引用した、とうようさんの公演評にあったクレイの「深い声」「練り上げた節まわし」「強烈なリズム感覚」「みごとにコントロールされたダイナミックス」「歌と一体化した自然なアクション」は全てこのドラマツルギ—を構成する要素だ。
とうようさんは、確か別の文章でオーティス・レディングのライブについて「押したり、引いたり」という表現を使っていたが、僕の感覚では「押さえ込み、引きあげる」と言った方がしっくりくる。
それはサム・クックのハーレム・スクエアでも同様だ。
具体的方法はそれぞれだが、優れた黒人音楽家、特に南部のゴスペルにルーツをもつ人はこのドラマツルギーによってパフォーマンスを行うと断言してもよい。
しかし何故このようなドラマツルギーが生みだすことできたのか、それは何を意味しているのか、僕には長年の疑問だった。
その疑問が少し解けたのは90年代初めにジェームズ・ブラウンのLIVEビデオで「マントショー」を観ていたときだ。
※
マントショーはブラウンのライブの終盤に歌われる「プリーズ、プリーズ、プリーズ(PLEASE、PLEASE、PLEASE)」において行われ、海外ではCAPE ACTと呼ばれている。
曲は去って行こうとする恋人に対して、「Please, Please, Please, Darling Please, Don't (Go), whoa oh yeah, oh. I love you so」(お願いだ、お願いだ、お願いだ、行かないでくれ、こんなに愛しているんだ)というフレーズをワンコードで繰り返す単純なものだ。
ブラウンは曲の途中、力尽きて突然崩れ落ちひざまづく。そこに司会(MC)のダニーレイがマントを持って現れ、やさしくマントを被せてブラウンを舞台袖に連れて行こうとするが、それまで息も絶え絶えで動けなかったブラウンはまるでマシラのごとくマントを振り払い、再び、「Please, Please, Please, Darling Please, Don't (Go), whoa oh yeah, oh. I love you so」と歌いだす。これを延々とり返すジェームズ・ブラウンの代名詞とでも言うべきパフォーマンスだ。
もともとは、1940年代から50年代にかけて貴族風の豪華な服を身にまとって試合を行い人気のあったプロレスラーのゴージャス・ジョージが相手からやられ倒れると、彼のマネージャーがスパンコールのついたド派手なガウンを持ってきて彼に掛けるや、突然蘇り反撃するというギミックをブラウンが見て取り入れたという。
ジェームズ・ブラウンは70年代に一時人気が衰えるが、「ブルース・ブラザーズ」「ロッキー」への映画出演、ラッパーによるサンプリングでヒップホップ世代からも絶大なリスペクトを受けたこと、イギリスでのクリス・ホワイトによる音源発掘、等等、80年代に蘇り、黒人や黒人音楽ファン以外にも知られる存在となるとともに、彼のマントショーも一般に広く認知されるようになった。
日本でもジェームズ・ブラウンはインスタントラーメンのCMに出演し、マントショーは後年「あまちゃん」で再現された程だ。ミソッパ!
ただ、大半の人はマントショーを「ギャグ」又は「コミックショー」と思っていたはずだ。
1959年、この「行為」を最初に観た黒人達もおそらく笑ったと思う。しかし同時に猛烈に感動したはずだ。何故なら、マントショーは本質的に「キリストの死と再生」の再現儀式に他ならないからだ。
この去っていく恋人を追いかけ打ちひしがれ動けなくなった男にマントを掛けると立ち上がり蘇り再び唄い出すという一連の行為は確かにチープでコミックだ。
しかしそのチープさはチープがゆえ、儀礼の虚飾を剥ぎ取り行為の本質をむき出しに露呈しながらも隠蔽している。
十字架にかけられたイエスは最後に大声で叫んだ。「エリ、エリ、レマ、サバクタニ。わが神よ、なぜ私を見捨てるのだ」と。(マタイ福音書)
マントは「聖骸布」であり、マントショーは「オカルト(隠されたもの)」だ。
※
1959年はアメリカ黒人音楽史上極めて重要な年だった。マイルス・ディヴィスが「KIND OF BLUE」を、レイ・チャールズが「WHA'D I SAY」を、ジェームズ・ブラウンが「PLEASE、PLAEASE、PLEASE」をリリースし、ジャズに「モード」が、R&Bに「ゴスペル」が史上初めて導入された年なのだ。
ブラウンはこのゴスペルの最も基本的なスタイルの曲でマントショーを繰り返し何度も観客の心を引きずり回した後、1960年代初頭ならば「NIGHT TRANE」で、ファンク時代以降は「OUT OF SIGHT」や「PAPA'S GOT NEW BAG」、「I'VE GOT FEELING」を唄い踊り観客を爆発させる。これが、ジェームズ・ブラウンの「ドラマツルギー」であり、それは「死と再生」の再現だ。
僕はこのことを、ジェームズ・ブラウンのLIVEビデオを観て直観した。それ以降はソウルやゴスペル、さらにブルース、ジャズまで全ての黒人音楽においてのライブを「死と再生を再現するためのドラマツルギー」として考えるようになった。
このことに関連して、僕は長年ゴスペルにおける「シャウト(SHOUT)」という意味がよくわからなかった。
ゴスペルで「シャウト(SHOUT)」と言えばゴスペル歌手の「叫ぶ唱法」または、信者達がトランス状態で「叫ぶ」ことを意味していると思われるだろうが、ゴスペルレコードのライナーノーツやゴスペル〜アメリカ黒人キリスト教に関する本を読んでいていると、例えば、
「(ロックなどの世俗音楽で)新しく登場したダンスのステップは聖なる「勝利」の踊り、シャウトを真似たものだ。」
「この曲は古くからのリングシャウト形式による」
というような使い方をされており意味がまるでわからなかった。
調べていくと奴隷制時時代の黒人達が夜中に集まり輪になって回りながらコール・アンド・レスポンス方式で霊歌を歌ったことを「リング・シャウト」と言い、さらに宗教集会で唄ったり祈り踊る行為その他、黒人協会での礼拝に関する行為がすべて「シャウト」なのだ。
このことはウェルズ恵子さんの著書「魂を揺さぶる歌に出会う(岩波ジュニア新書)」に詳しい。(この本はゴスペルに限らず、アメリカ黒人のルーツミュージックについて解りやすく、今まで知らないことをいろいろと教えてくれる黒人音楽ファン必読の好著です。)
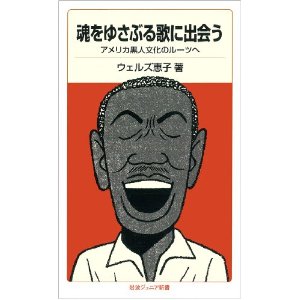
魂をゆさぶる歌に出会う
アメリカ黒人文化のルーツへ
ウェルズ 恵子
【Amazon のBook情報】
だから、前述したドラマツルギーも「シャウト」のためにあるのだ。
それでは、黒人達は何故「シャウト」を行うのだろうか。
それは「聖霊(HOLY SPIRIT/HOLY GHOST」を呼ぶためだ。
※
次回(117回)に続きます。
※
Live at the Harlem Square Club, 1963
Sam Cooke
1.Feel It (Sam Cooke)
2.Chain Gang (Cooke)
3.Cupid (Cooke)
4.Medley: It's All Right / For Sentimental Reasons
5.Twistin' the Night Away (Cooke)
6.Somebody Have Mercy (Cooke)
7.Bring It On Home to Me (Cooke)
8.Nothing Can Change This Love (Cooke)
9.Having a Party (Cooke)
Sam Cooke - vocals
Clifton White - guitar
Cornell Dupree - guitar
Jimmy Lewis - bass guitar
Albert June Gardner - drums
George Stubbs - piano
King Curtis - saxophone
Tate Houston - saxophone
Bob Simpson - recorded by
Tony Salvatore - recorded by
Steve Rosenthal - mixing
Tom Psipsikas - assistant engineer
Hugo & Luigi - supervised by
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
