
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
日本のジャズ
撰者:平田憲彦

あ、来てたんですか。
ええ、さっき。平田さん、仕事?
なんだかバタバタで。吉田さんも?
いやあ、いつもとかわりませんよ。
(ジントニックおねがいします)
ところでこの間のコラム、いいっすねえ(笑)
いやあ(笑)
とうとう来ましたか、ミシシッピって感じで。
ありがとうございます(笑)
吉田さんのおかげで、ゴスペル熱再燃。
ところで次は平田さんですよね。もう書いたの?
なんとか。
次は?
またヘタな小説にしようかと思って。
(ラムのソーダ割り、おかわりください)
また実話?
違いますよ(笑)、全部フィクション(笑)
マイルスのあれ、あんなことが平田さんにあったのかと(笑)
違いますって、あれも創作ですよ。ちょっと上手に書きすぎたかな、なんて(笑)
次は何を?
日本のジャズです。
なるほど。
吉田さんを差し置いて書いちゃいました(笑)
というと?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
小説のような物語
ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニィモア
Don't Get Around Much Anymore
※
あの裏路地にこんな店があるなんて、たぶん知ってる人は少ないはずだ。扉を開けると、いつもの冴えない笑顔が迎えてくれる。
「今日は遅いじゃない」
「たまにはこういう日もあるんだよ」
などと言いながら、僕はぎこちなくカウンターに着く。もうみんな帰ってしまったんだろう。さすがに2時だ。ひとりくらいはいるだろうと思ってた。
「もしかしたらもう閉めたかなって思ったよ」
「そうだったらいいんだけどね」
「どういう意味だよ(笑)」
「そういうんじゃないって。2時には閉められるくらいだったら、もうちょっと普通の生活が出来るかもなあ、って思っただけ」
「十分普通だよ」
レコード棚をごそごそしながら、
「何飲む?」
客は僕しかいないのに、なんだか忙しそうだ。
「たまには二階堂のお湯割にするかな」
「へえ、珍しいね」
「ジントニックばかりじゃ、飽きるだろ」
「誰が?」
「圭子が」
「私が飲むんだったら飽きるかもね」
「おごるよ」
「じゃ、ジントニック(笑)」
二階堂の熱いお湯割と、氷がいっぱい入ったゴードンのジントニックで僕らは乾杯した。
「なあ、『ぬるいビールと冷たい女』って曲知ってる?」
「ははは(笑)、こないだあんたの文章を読んだよ」
「なんだ、知ってたか」
「あのアルバムを取り上げるなんて、やっぱりあんた変わってる」
そう言いながら、圭子はひとくちジントニックを飲んでレコードをかけた。
ピアノの音、そして、浅川マキさんの声。
これは『わたしの金曜日』だ。『MAKI VI』の一曲目。
「持ってたんだ」
「これは好き。大好き」
圭子はどうやら二階堂を濃い目に割ったみたいだ。染み入る。
「あのさ、女としてこの曲を聞いて、どう思うの?」
「つまんないコト聞くね」
「つまんなくないさ。これって、娼婦になったばかりの女の子の歌だろ」
「だから?」
「え、怒った?」
「怒るわけないでしょ」

この曲は切ない。女の弱さと強さ、男の馬鹿さとズルさを、この曲は最小限の言葉で最大の表現をしている。『MAKI VI』は、浅川マキさんと山下洋輔さんのデュオから始まる。
このアルバムは、ジャズという音楽が日本語に昇華した傑作だと僕は思う。でも、そういう理屈っぽい話を圭子は嫌がる。純粋に音楽を音楽として聴きたがる。
「これ、泣きそうになるんだ、あたし」
ちょうど『ここは何処ですか?』という歌詞のところで、圭子はつぶやいた。
ブルース、そしてジャズ。
日本にいる僕らには近くて遠い音楽だ。でも、浅川マキさんのこんなアルバムを聴くと、日本人のジャズという音楽がリアルに感じてしまう。それは、日本人プレイヤーがどこまでジャズを演奏できるか、ということではなく、日本人には日本人のジャズがあるんだということを。
次々と繰り出されてるマキさんと山下さんたちのグルーヴ。
「すごいスウィング感だな」
「フォービートと日本語の結婚?(笑)」
「結婚というより同棲かも」
ひとくち飲んだ圭子は少し目を丸くして、
「上手いこと言うじゃない」
マキさんの日本語と、山下洋輔さんたちの日本人ミュージシャンが演奏するジャズが、これほど見事にとけあってるなんて。
コピーでもカバーでもなく、日本人のジャズ。
中国からやってきた『漢字』という文化を租借しながら『ひらかな』を生み出したような、ジャズという米国文化を日本に取り入れながら、日本の文化に融合させたような、そんな強さを感じる。
曲は『戸を叩くのは、誰』になった。
「たまんないね」
「なんか、一曲目とつながったね」
「うん、明らかにジャズ、でも日本って感じ」
「歌詞が、やっぱりすごいんだよ。愛だの恋だの、好きとかどうとか、そういう言葉がまったく出てこないのに、すっごく人恋しい気持ちが伝わってくる」
「ほんとに」
「マキさんって、はじめは黒人霊歌を歌いたかったんだってね」
「それってゴスペルってこと?」
「俺もそう思ったんだけど、ゴスペルと黒人霊歌は、ちょっと違う」
「詳しいじゃん」
「いや、マキさんがラジオのインタビューでそう言ってた」
「なんだ(笑)」
スウィング、4ビート、ブルース。大げさな言い方かもしれないが、浅川マキというシンガーが、当時の日本人ジャズミュージシャンたちとのセッションの中から、日本のジャズをスタート地点に立たせたというような気がした。米国のものまねではない、日本人による日本人のためのジャズを。
「ねえ、もう一杯もらっていい?」
※
マキさんとともに夜は3時に近づいた。
最後のナンバー『ボロと古鉄』は、どことなくコルトレーンの『マイ・フェイバリット・シングス』を連想させる。
マキさんの歌も良いし、山下さんも、バンド全体も、ドライブしてる。気持ちいい。
「日本のジャズなんだけどさ」
二杯目も濃い。さっきより濃いんじゃないか?
「だからさ、あたしわかんないんだよ、そういうムツカシイ話」
「そうじゃなくて、って言っても同じか(笑)」
「あんたたちはムツカシイ事ばかり話してんのよ。黙って聴けばいいんじゃないの?」
「なんかね、しゃべりたくなってくるんだよ、何がどう良いかとかね」
「しゃべって音楽が良く聴こえるの?」
「いや、変わんないと思う」
「ヘンなの」
二階堂は美味い。谷さんはいつも二階堂を飲んでた。でも、『パッション』にいる時は、いつもハーパーだった。僕は長い間フォアローゼズだった。今ではちょっと立派になってジャック・ダニエルを飲んでるけど。
「最近、谷さんどう?」
「来ないねえ」
「結婚したんだよ」
「知ってる」
このアルバムは、マキさんのジャズアルバムでもあり、ブルースアルバムでもあるんだ。
「でも結婚したら飲みに行けないってわけじゃないでしょ、谷さんみたいな遊び人なら」
「まあ、でも二回目だからね」
「それに相手は一回目だし?」
突然、威勢のいいバンジョーの音が僕たちを遮った。
「イイのかけるねえ」
「あたしさ、これを初めて聴いたのが『パッション』だったんだ」
「俺もその時一緒にいたよ」
「一緒に歌ってたよね」
「抜けるような空の下、って大合唱だったよ。真夜中の真っ暗なジャズバーで」
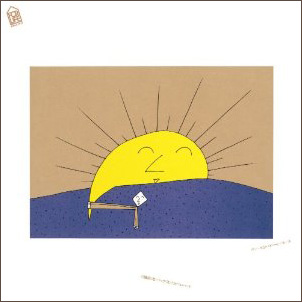
僕はそれまで高田渡というシンガーをよく知らなかった。アルバムも持ってなかった。ましてや、このヒルトップ・ストリングスバンドなんて、名前も聞いたことがなかった。
でも『パッション』で荻野さんが持ち込みでかけたこのアルバムは、まいった。一発で夢中になって翌日には買いに行った。
「このアルバム聴くとね、男の人って可愛いなあ、なんてね」
「思った?」
「うん。いったい、君はどこに行きたいの? って聞きたくなる」
「そうだねえ。行きたいところがあるっていうよりは、今いるここを離れたい、って感覚じゃないのかな」
もう、どう聴いてもニューオリンズジャズ。そして、全曲が日本語。それが、びっくりするほどマッチしてる。
よくよく聴くと、全曲がニューオリンズジャズではなく、フォークソング風なナンバーも混じってるが、なにしろバンドが絵に描いたようなニューオリンズジャズバンドなので、出てくる音もディキシーなのだ。まるでサッチモのホットファイブ、というと言い過ぎかな。
バンジョーとウッドベースがとりわけ素晴らしい。
圭子がこのアルバムに『放浪』を感じ取ったとおり、なんとも切なく、そしてリアルな心情が淡々と歌われ、語るように、ささやくように、ゆるいブルースが流れる。
「この曲って、ブルース?」
「典型的ブルースだよ」
「どこが典型的なの」
「スリーコードで12小節」
「え?」
「例えば『ストーミー・マンデー』は、12小節だけどコードは6つあるし、進行も1・4・5じゃない」
「そう言われてもよくわかんないけど」
『夜汽車のブルース』は、スローテンポのウッドベースだけで始まって徐々に楽器が増えていき、最後はニューオリンズジャズバンド全体で賑やかに終わるという、見事なブルースナンバー。バンジョーとマンドリンも味わい深いし、歌詞も泣かせる。
この曲を家で聴くとき、僕はつい一緒にギターを弾いてしまう。
「なんか、懐かしい感じ」
『ダイナ』にしろ、『猿股の唄』にしろ、歌詞が本当に素晴らしいけど、そりゃそうだと納得するのは、サトウハチローさん、金子光晴さんという詩人の作品が元になっているからだろう。『座布団』は山之内獏さんの作詞。
でも、それだけすごい文学者の作詞だけじゃなく、高田さん、佐久間さん、小林さんの作詞も、ほんとうに心にしみ入る。
浅川マキさんの曲も歌詞がなんともいえず良いんだけど、この高田渡さんのジャズは、ニューオリンズのディキシーサウンドに日本語を付け、しかもそれが取って付けた感じじゃなくて最初 からここにあったんじゃないかと思えるくらいの自然さが驚く。
「この高田渡さん、酒に合うなあ」
ふいに圭子は、ビックリするアルバムを差し出した。
吾妻光良さんのスウィンギング・バッパーズ。
※
「驚いたよ」
「へへへ、かけようか?」
「頼むよ」
僕も何枚か持ってるけど、圭子がかけたのは吾妻さんの三枚目、全曲日本語になった最初のアルバム。強烈にして冗談のようなバカバカしいイキオイに満ちた、日本の誇るべきジャンプブルース、そしてスウィングジャズの生きる化石みたいなバンド。

「久しぶりだよ、バッパーズを聴くのは」
「実はあたしもなんだ」
「こんなバンド、ないよなあ。歌詞がえげつない」
圭子は笑いをかみ殺しながら
「しかし、ヘタねえ」
「え?」
「ほんと、言いたくないんだけど」
「何がだよ?」
「こんなヘタな歌で、よくレコード出せたよね」
「なあ、圭子……」
「これって、子供の歌と変わんないよ」
「あのな、歌はね、上手いとかヘタとか関係ないんだ」
「バカねえ、あんた」
「?」
「子供の歌はヘタだよ。でも、すっごく良いじゃない」
「ああ、そういうことか」
「こんないい歳して、大人なのに、こんなヘタな歌をレコードにするってのが素敵なのよ」
「まあなあ」
「子供の歌はヘタだよ。けどすっごく伝わるんだ。程よく上手なプロの歌手なんか及びも付かないくらい、ヘタだけど子供の歌は本物なんだよ」
「それは、そうだな」
「吾妻さんの歌は、そういう感じなんだよね。だから聴いてて共感しちゃう。なんで?って思うんだけどさ。自分でもよくわかんないんだけど、それでも、イェーって言っちゃうんだ。レコードに向かって(笑)」
ああ、僕は吾妻さんに嫉妬してしまいそうだ。
「あんたの字って、びっくりするくらいヘタでしょ」
「なんだよいきなり」
「あんた、もう50歳でしょ、でもあんなヘタな字しか書けない」
「悪かったよ(笑)」
「それといっしょ。あんたの字はとってもヘタだけど、見ていて安心するんだ」
「それって、褒めてんのか?」
圭子にも酒が回ってきたか、バッパーズのスウィングが酔わせるんだろうか。
しかしくだらない事歌ってるなあ。生活臭ありすぎ。でも妙に共感してしまう。大友克洋さんが『AKIRA』を描く前の時代も、こんな生活臭さ満載だった。本質的に似てるな、なんとなく。
「バッパーズの曲は、ヘンなのよ。音はスウィングジャズなのに、歌詞がいかにも受けねらいで。ふふふ、苦労して当てはめたの?って勘ぐっちゃうくらい。でもね、そこも計算してるのかなって思っちゃうんだ」
「というと?」
「つまりね、こんな歌で、そこそこ上手な演奏で、歌詞もなんとなくワザとらしい。ジャズっぽくブルースっぽくやって、なんかいい加減なんだけど、そのいい加減ということが、音楽なんじゃないの?って言ってるような気がするんだ」
「いい加減?」
「アマチュアで音楽やってる人たちって、なんだかみんなマジメでしょ。真剣でしょ。CD出さなきゃだめだとか、ホールでライブ出来なきゃダメだとか、なんか自分で自分を型にハメちゃってるような気がするんだ。でも吾妻さんはそういうのを全部置いといて、適当でいいから、ヘタでもいいから、出来ちゃうんだぜ、って言ってる。アマチュアなんだよ、好きな音を出そうぜ、って言ってるような気がする」
「……」
「真剣すぎて空回りするより、適当に気持ちいい音を出そうよ、っていうか」
「あのな、言いたいことはわかるけど、売れなくても真剣にやってるプロをバカにしてるんじゃないか、圭子は」
「だから、逆なんだって。アマチュアのことを言ってるの。バッパーズは全員昼間はサラリーマンでしょ」
「そうらしいね」
「アマチュアの極みなんだよ、バッパーズは」
「音楽はアマチュアもプロも、実は関係ないんだよ」
「そうなの?」
「そうだよ!(笑)」
「それは違うと思うな、あたし」
「そうか?」
「プロは、稼ぐんだよ。音楽で。稼がなきゃいけないんだよ。好きな事だけやってられないんだよ。あたしがこうやってお酒をつくってるようにね。こんな時間まで」
「あのさ、わかった、帰るよ」
「だから違うって。まだいてよ」
「俺が間違ってるか…」
「間違ってないよ。あたしが言いたいのは、プロはお金を稼ぐことが重要で、アマチュアは音楽でお金を稼がなくても生きていけるでしょ、ってこと。だったら、生真面目にやるんじゃなくて、自由に、適当にやったらいいんだよ。お客さんのことを意識しすぎないで、自由にやったらいいんだ。楽しんでくれて、付いてくれるお客さんがいたら、それはラッキーだよ。でもプロは違うんだよ。お客さんを無視して音楽は出来ないんだ。お客さんがつかなかったら、自分の演奏や歌にお金を払ってくれる人がいなかったら、食っていけない。生きていけないんだよ」
僕よりも圭子が酔っぱらったみたいだ。
ジントニックが効き過ぎたかな。
「圭子、鳥が鳴いてるぞ」
「またやっちゃった …」
「晴れだよ、今日は」
「ちょっと外を見てきて」
このキーンとした空気。朝の5時半、青空、そして空気が冷たい。でも優しい。それは朝まで飲んだ酔っぱらいだけに優しいんだ、と思いたい。
「あんた、帰れるの?」
「もう始発は動いてるよ」
「なんだ、そっか」
「送ってくよ」
「なに言ってんの。あたしは歩いて帰れるのよ」
「知ってるよ。だから途中まで」
「ヘンなこと考えてる」
「考えてない(笑)、最近はひったくりや通り魔が多いんだよ」
「心配なんかしてないくせに」
「違うって。おまえ、飲み過ぎだよ」
「飲んでないよ。なに言ってんのよ」
タクシーを捕まえる距離じゃないし、近すぎてまた柄の悪い運転手に悪態つかれるのはごめんなので、圭子を連れて歩く。
「しかし圭子、よくあのアルバム持ってたね。すごいよ。俺は全部持ってたんだけど、気が付いたら無くなってたんだよね」
「へえ」
「確かに持ってたんだけど…」
「あんた、覚えてないんだ」
「え?」
「今日かけたアルバム」
「全部いいレコードだよ」
「あれ、あたしのじゃないよ」
「なに、借りたの?」
「バカねえ、ほんとに忘れたの…?」
ちょっと待てよ、今日の3枚。
あれは、確かに持ってた。でも気が付いたら家から無くなってた。いつ無くなったんだ?
「ねえ、カバンとって」
「どっち?」
「赤いほう」
僕はこの瞬間思い出してしまった。
そうだ、そうだった…
うつろな目で圭子がつぶやく。
「まだ忘れてるのあるよ… トム・ウェイツの、あのライブ、あんたがこの間紹介してたアレ…」
そうだ、トムのアルバムを紹介しようと思ってレコードラックを探したら見あたらず、僕は新たに買ったのだった。
「圭子、他に何がある?」
「思い出せないくらい…」
ヘロヘロに酔っぱらった圭子の代わりに、僕はドアの鍵を回した。
※
この物語はフィクションです。
でも、取り上げている音楽はノンフィクションです。
筆者
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
物語に出てきたアルバム

MAKIVI
浅川マキ
【Amazon のCD情報】
浅川マキ :ヴォーカル
山下洋輔 :ピアノ
森山威男 :ドラム
坂田 明 :アルトサックス、クラリネット
稲葉国光 :ベース
1 わたしの金曜日
2 港町
3 ジン・ハウス・ブルース
4 キャバレー
5 あんな女ははじめてのブルース
6 今夜はおしまい
7 戸を叩くのは、誰
8 ボロと古鉄
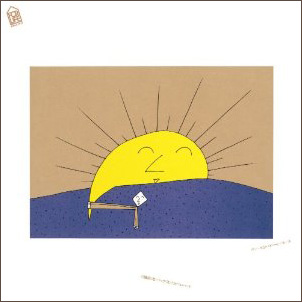
ヴァーボン・ストリート・ブルース
高田 渡 & ヒルトップ・ストリングス・バンド
【Amazon のCD情報】
高田 渡 :ヴォーカル、ギター、ウクレレ、マンドリン、オートハープ
小林 清 :ヴォーカル、バンジョー、ウクレレ
佐久間順平 :マンドリン、フィドル、ブズーキー
大庭昌浩 :ベース
外山喜雄 :トランペット
後藤雅広 :クラリネット
池田幸太郎 :トロンボーン、バンドネオン
池田光夫 :バンドネオン
1 ヴァーボン・ストリート・ブルース
2 夜汽車のブルース
3 ウィスキーの唄
4 シグナルは青に変わり汽車は出てゆく
5 G・M・G(グラフィス・マンドリン・ソサエティ)
6 その向こうの
7 ダイナ
8 猿股の唄
9 座布団
10 すかんぽ(哀れな草)
11 リンゴの木の下でドミニクは世界の日の出を待っていた

Squeezin' and Blowin'
吾妻光良 & The Swinging Boppers
【Amazon のCD情報】
吾妻光良 :ヴォーカル、ギター
名取茂夫 :トランペット
近 尚也 :トランペット
冨田芳正 :トランペット
西島泰介 :トロンボーン
西川文二 :テナーサックス
糸井将博 :アルトサックス
渡辺康蔵 :アルト&テナーサックス
山口三平 :バリトンサックス
早崎詩生 :ピアノ
牧 裕 :ウッドベース
岡地曙裕 :ドラム
1 やっぱり肉を食おう
2 バッチグー
3 嫁の里帰り
4 中華 Baby
5 おもて寒いよね
6 コネが無きゃ
7 俺のカツ丼
8 ワイノニーを聴きながら
9 道徳 HOP
10 知らぬまに心さわぐ
11 刈り上げママ
12 飲むのはやめとこう
13 小学校のあの娘
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
