
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
管楽器とピアノのデュオ
撰者:大橋 郁

今回は、管楽器とピアノという組み合わせによるデュオ作品の中から私が愛聴している作品をいくつかを紹介したい。
デュオとは、文字通り二人による二つの楽器だけで、完結させる形態である。ピアノとギターのデュオや、ピアノとベースのデュオ、ギターとベースのデュオなど、世の中には一般的なコンボ編成に拠らないデュオ作品というものがいくつかある。二人だけでダレることなく、飽きさせず、尚かつ変化に富んだ作品を作り上げるのは、相当腕に自信のある人でなければ難しい。
そんなデュオ演奏とは、演奏者にとってはどういう意味をもつのであろうか。
ベースとドラムの伴奏にしっかりと支えられた心地よさの中に居るバンド演奏と違い、デュオの場合、パートナーは自分の出す音の全てを聞いていてくれている。一音一音をより一層大切にした対応が求められる。そしてパートナーの出す音を聞いているのは、観客を除けば自分ただ一人だ。パートナーの出す音をバンドとして共有するのでなく、自分一人だけが独り占めできるという幸福感と同時に、一音も聞き逃してはならない、という緊張感。そして二人だけのおしゃべりをとことん楽しめる、ということへの感謝。パートナーに反応出来るのは自分ただ一人だ。パートナーを活かせるのは自分しかいない。そして自分がどう反応したか、パートナーにも全て聞こえている。二人だけの会話で作る音楽は簡単に良くもなり、下らなくもなる。
そのようなデュオという形態の中、管楽器とピアノによるデュオは、「主と従」の関係にもなれば、「主と主」の関係になったりもする。漫才風に言えば「掛け合い」である。世の中にあるデュオというジャンルの中から、その一分野であるピアノと管楽器によるデュオの美しい「対話」や「会話」を愛聴盤の中から5枚ピックアップしてみた。

Oscar Peterson & Dizzy Gillespie
【Amazon のディスク情報】
1974年の録音。これは、パブロレコードの主宰ノーマン・グランツが、オスカー・ピーターソン(p)と5人のトランペッターとのそれぞれのデュオ作品を録音するというシリーズ企画の中で、5枚制作されたうちの1枚。残りの4人は、ハリー・エディソン、ジョン・ファディス、ロイ・エルドリッジ、クラーク・テリーだ。実は他の4枚は聴いていない。というのも、これら一連のシリーズが発売された1976年当時、私は高校1年生。5枚全てを揃える財力などもちろんなく、せめてどれか一枚をと思ってさしたる理由もなく選んだのがこの1枚だった。
そもそも、ディジー・ガレスピー(tp)という人は、アメリカ・ジャズ界に多いに貢献してきた人であり、超大御所的存在としてマイルスや、クリフォード・ブラウン始め、ほとんどのモダン・トランペット奏者の目標となってきた人である。日本でも、パーカーと共にバップの創始者的存在として崇め奉られてきた。しかし、名前の偉大さが先行し過ぎて、実際の演奏を身近に楽しむということが、まるで博物館に出かけて行くことのように、大層なイベントになってしまった感がある。一方のピーターソンは、誰にでも親しめ、解りやすく大衆から愛されるピアニストであり、二人の接点はあまりないように思える。しかし、この二人は共にヴァーヴ・レーベルにおけるJ.A.T.P.(Jazz at the Philharmonic)オール・スターズの興業で各地を同行していた仲であり、古くからお互いをよく知る間柄だったのであろう。
このアルバムは、リラックス感というよりも緩急使い分けた緊張感が漂う曲が多い。ディジーのトランペットはもの凄い勢いでまるでその場の空気を切り裂くかのように、切り込んでくる。そのスリルがたまらないのだ。ピーターソンとガレスピーは互いに相手の音に対し、瞬時に反応し合っている。コンボ演奏にはないデュオの醍醐味であろう。ピーターソンの参加作品の中では、異色作の部類といってもいい。
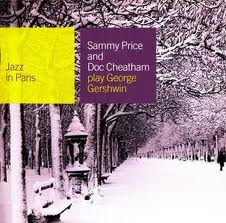
Plays George Gershwin
Sammy Price & Doc Cheatham
【Amazon のディスク情報】
サミー・プライス(1908-92)とドク・チータム(1905-97)は共に、サッチモに近い世代。このアルバムは、1曲目から16曲目までがプライスのピアノ・ソロで、1956年録音。残る17曲目から24曲目までが、プライスとドク・チータムのデュオで、こちらは1958年にパリで録音されている。
サミー・プライス(p)は、どちらかというとブギ・ウギ、ジャンプ系のピアニスト。 『二人でお茶を』『柳よ泣いておくれ』などのジャズ・スタンダードもブギ・ウギ風に仕立てられていて、古い録音の割には今となっては新鮮で面白いアレンジだ。 ドク・チータム(tp)については、かつてこのコラムの第65回でライオネル・ハンプトン楽団について書いたときに触れた。8分音符を主体とした、優しく解りやすい、流れるようなフレーズを吹く人だ。この人は、チック・ウェッブ楽団、キャブ・キャロウェイ楽団を始めとして沢山のバンドを渡り歩いており、ディキシーもスイングもラテンもこなした人のようだ。サミー・プライス(p)はテキサス出身らしく、ブギ・ウギ、ジャンプ、時にはラグタイム風という古き良きアメリカン・オールド・スタイルを貫いており、ドク・チータムとはピッタリ合っている。
二人の育った20世紀初頭の南部や西部には旅廻りの楽団も多くやってきたことだろう。そんな黒人コミュニティ向けの内容の濃いブラックニュージックを聞き、時には一緒に演奏させてもらって育っていったのだろう。このアルバムは、そんな田舎町での巡業中、お店の閉店後にゆったりとした気分で行われたアフター・アワー・セッションのようなリラックスした雰囲気伝わってくる。
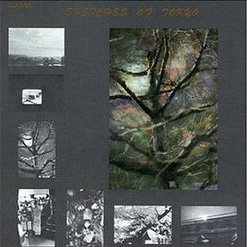
Sketches of Tokyo
Hohn Hicks &David Murray
【Amazon のディスク情報】
1985年4月11日、デヴィッド・マレイ(ts)と、ジョン・ヒックス(p)が来日中に東京で録音し、日本のDIWレーベルからリリースされたデュオ作品。
ジョン・ヒックスは1941年ジョージア州アトランタ生まれ。父親は牧師。母親はピアノも弾く教師という環境に育った。リトル・ミントンのブルース・バンド、ジャズ・メッセンジャーズにも参加している。後に、チャールス・トリバー(tp)のミュージック・インクや、当コラムの第30回で松井さんが紹介したファラオ・サンダース(ts)カルテットにも参加した。マッコイ・タイナーを敬愛しているとのことだが、マッコイ以上に幅や音の広がりがあるように思える。
1曲目はセロニアス・モンクの「エピストロフィー」。意味は「結句反復」といって文章の最後を同じように繰り返す手法。この1曲のみはジョン・ヒックスによるピアノ・ソロで演奏される。2曲目の「ブルース・イン・ザ・ポケット」以降は、もうマレイ節全開!!聴いていて、気持ちいいくらいにフリークトーンが冴えまくる。そして圧巻は3曲目にあるコルトレーンの「ネイマ」。ジョン・ヒックスのコンテンポラリーなサポートに乗って、マレイが自由に吠えまくる感じ。しかし、ただ吠えるだけではない。とてつもなく深く、そして美しい。
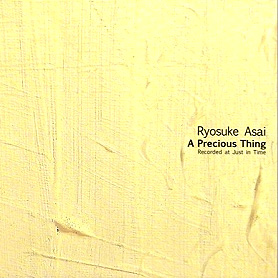
A Precious Thing
浅井良将
関西を基盤に活躍する浅井良将(as)が、5人のピアニストと2曲ずつ計10曲を録音した作品。浅井は1985年兵庫県神戸市に生まれ、甲南中学・高校でビッグバンドに所属した。関西の尖鋭的若手ミュージシャンで結成されたジンジャー・ブレッド・ボーイズを始め、様々なグループで活動している。
2曲目に大友孝彰(p)とのデュオによるFu-fu Genka(夫婦喧嘩)という曲がある。
4小節ずつ交換をしながら掛け合いをする部分が、まるで夫婦の言い争いを表しているようで面白い。互いの言葉に、いったんは同意したり、噛みついたりしながら夫婦喧嘩が続く。しかし最終部分ではさっきまでの夫婦喧嘩が嘘のように仲直りし、一糸乱れぬ見事なユニゾンとなる。永年連れ添い、似た者同士となった夫婦の絆のようだ。8曲目の「フィール・ライク・メイキング・ラヴ」と共に、本アルバム中屈指の出来だ。
この曲は大友孝彰(p)が書いた曲である。大友も1986年生まれで、浅井とは同世代のピアニスト。
余談ではあるが、大阪〜別府航路と、神戸〜大分航路を運航するフェリーさんふらわあでは、毎週金曜日の下り便と土曜日の上り便で「さんふらわあジャズナイト」を実施しており、乗船者は誰でも無料で、関西の意欲的なミュージシャンの演奏を聴くことが出来る。浅井と大友も、このジャズ・ナイトに時折顔を見せるメンバーである。
(参考:フェリーさんふらわあ「ジャズ・ナイト」のスケジュール)
http://www.ferry-sunflower.co.jp/jazz/index.html

People Time
Stan Gets & Kenny Barron
【Amazon のディスク情報】
このアルバムは、当コラムの第93回において、北欧のコペンハーゲンのジャズ・クラブ「カフェ・モンマルトル」で録音したものを紹介するシリーズの中で登場させてしまっているので、ここでは多くを書かない。しかし、私が持っているデュオものの中でも最も気に入っているアルバムのひとつであり、大推薦盤であることを再度強調しておきたい。とにかく、二人の「対話」というか「会話」による、二人だけの恍惚の世界。そして、ケニー・バロンの屈託なくおしゃべりするようなピアノとスタン・ゲッツの流麗なサックス。絶品である。
ケニー・バロンは、ピアノ・トリオの名作も多いが、ドラムとベースを伴わない方が味わい深いかも知れない。ピアノとサックスだけのシンプルな編成でありながら、最初から最後まで飽きることなく一気に聴ける。そして聴き終わった後は、まるで魔法にかかったような満ち足りた気分になれる。大傑作である。
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
