
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
ロバート・グラスパー
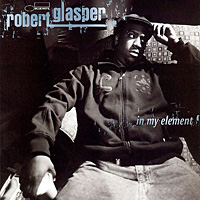
【Amazon のCD情報】
インターネットが発達し、通販で多くの物が簡単に手に入るようになってからというもの、音楽も過去から現在が水平に繋がった。つまり、2012年に作曲され、録音されたレディガガの新作と、1742年に作曲され1955年にグールドによって録音されたバッハのゴルトベルグ変奏曲が、同じ音楽商品としてアマゾンなどの通販サイトの同じ画面に現れるというわけである。
レコードショップでは、少なくとも売り場を移動するという『運動』が必要だった。ポップス売り場のレディガガから、クラシック売り場のグールドまで、カラダを動かして歩き、棚からお目当てを探す、あるいは、ぼんやりと棚を見つめながら、思わぬ発見をするなど、手足を使った運動と眼球運動によって喚起された思考が呼び起こす新たな音楽との邂逅というドラマがあったのだ。
現在でもそういう身体運動が演繹する音楽への導線は存在する。しかし、それも希少な体験として語り継がれてしまうような空気すら感じるインターネットの水平化なのである。インターネットでは、身体運動は不要だ。そんなことをしなくても、レディガガとグールドを容易に捜すことが出来るし、アマゾンが巧妙にプログラムしたシステムで『知らなかったアルバムに出会う』という疑似体験が本物の体験であるように昇華されてしまう現在である。ただ、それは否定されるよりもむしろ、好感すべき、歓迎すべき事として現在の音楽シーンはあるし、私もそう思う。
今我々は、かつて特権的だった音楽を知らなかったとしてもなんらそしりを受けることはないし、恥と思う必要もない。新しい音楽を知っているからと言って胸を張ることもなければ、新しい音楽やミュージシャンを知らないこと自体について偽悪的なそぶりを見せる必要もない。もちろん、その逆もしかりだ。
しかしながら、どうしても古い物、かつて本物という勲章が与えられたものについて、必要以上に擁護し、賞賛し、それがかえって新しい音楽から目を背けるということに肯定的となるばかりか、むしろ過去につくり出された音楽を神聖化してしまう危険性が常につきまとうのが、ジャズなりブルースなり、あるいはロックなりに魂を抜き取られた人々の行動なのだ。
実を言うと、私にもその傾向はある。2012年に録音されたブルースより、1938年に録音されたブルースに恋い焦がれ、その奥深さを必要以上に賞賛し、源流をさかのぼることをあたかも正しい音楽の聴き方であるかのように正当化してしまうという悪いクセが、私にはある。自由なんだから好きに聴けばいいじゃないか、という意見は正しいが、正しくない。なぜなら、1938年に録音されたブルースは、1938年当時は最新の音楽だったからだ。その音楽自体は、実は何も変わってはいないのである。にもかかわらず、聴いているこちらがあたかも時間と風雪に耐えて生き残った本物であるかのような屁理屈をこねて、1938年の音楽を特権化してしまっているだけのことなのだ。
音楽は音楽であり、新しいからとか、古いからとかで、その本質的な価値が変わるということはない。それをインターネットによる水平化が見事に暴いてくれたというわけだ。聴いたことのないアルバムは、全てがニューアルバム。とても素晴らしいことだと思う。
※
今回紹介するのは、1978年4月6日、テキサス州ヒューストン生まれのピアニストだ。名前をロバート・グラスパーという。幼年期から教会でピアノを弾き、ゴスペルやブルース、ジャズに触れ、2003年にアルバム『Mood』でデビューした。2005年にリリースしたセカンドアルバム『Canvas』からブルーノートという経歴である。
ファーストアルバムの1曲目にハービー・ハンコックの『Maiden Voyage』をリストしていることからも分かるとおり、その音楽性はハンコックに多大な影響を受けている。ニューヨークでは徐々に知名度を上げて頭角を現し、評判となっていたようだ。そのロバート・グラスパーが日本でも脚光を浴びるようになったのが、2012年である。5枚目のアルバム『Black Radio』が大きな注目を集めている。
このアルバムの伏線となっているのは4枚目のアルバム『Double-Booked』であることは間違いがないが、聴いていて実感するのは、2007年にリリースした3枚目の『In My Element』でロバート・グラスパーは何かとてつもない確実で不確実なものをつかんだのだろう、ということである。
2003年のデビューアルバムから2007年の『In My Element』に至るまで、ロバート・グラスパーはアコースティックジャズを演奏している。しかし、その音楽的質感は影響源であるハンコックそのものではなく、どこか浮遊しているのだ。ジャズピアノの歴史的流れであるエリントン、パウエル、マッコイ・タイナー、ピーターソンなどのスウィング感やブルースフィーリングとも違う、かといってビル・エヴァンスやハンコック、キース・ジャレットの流れとも違う。そのどれをも内包しているように感じるが、しかしどれとも違う。ただ、強烈なブラックミュージックの引力がある。
その答えが明らかになるのが4枚目の『Double-Booked』である。ロバート・グラスパーはヒップホップのスピリットをピアノに受け継いでいることを、『Double-Booked』では高らかに宣言している。
『Double-Booked』は、前半がアコースティックのピアノトリオ、後半がエレクトリックのヒップホップとなっている。だから『Double-Booked』というタイトルになったのだろう。通常は否定的に使われるコトバ『Double-Booked』は、ここでは圧倒的な肯定としてラベリングされている。
その『Double-Booked』の導火線が、『In My Element』というわけである。このアルバムは、ほとんど全てがアコースティックピアノトリオを中心とした編成で出来上がっているが、オーセンティックなジャズアルバムではない。どこか怪しい雰囲気、しかし泥臭くなくディープでもない斜に構えた不良感覚に満ちた音空間。これはあきらかにヒップホップの空気だ。裏道、脇道、暗がりに潜むサウンドであるが、しかし破滅的ではない。強いていえば優雅でエレガント。だが、デートのBGMにはとてもなりそうもない。
ここには、ヒップホップのスピリットを血流として取り込んだジャズピアノを聴くことが出来る。美しいが、BGMになることを頑なに拒む強さがある。反逆的だが破壊的ではない。かといって迎合しているわけでもない。静かに主張するブラックミュージックがピアノトリオとして具現化されている。
※
幼年期に教会でピアノを弾き、ゴスペルやブルースを聴きながら1998年に20歳になっていたロバート・グラスパーの耳には、すでにヒップホップが聞こえていたはずだ。ファーストアルバムをリリースした2003年から、5枚目のアルバムをリリースした2012年までの9年間は、まさしくインターネットが隆盛し、一般化し、ニューヨークタイムズが紙から電子に変容していく時代をそのままトレースする。しかし彼はジャズから離れなかった。
マイルス・デイヴィスがアコースティックジャズからエレクトリックジャズに進化し、ブラックコンテンポラリーを注入し、最後にはヒップヒップに向かったその魂は、マイルスが意識的に、恣意的に向き合った尊厳の証明であり進化の宿命であるように思うが、ロバート・グラスパーにはそのような気負いがあまり感じられない。結果として、アコースティックジャズからヒップホップへの進化をアルバムで具現化したその流れは、マイルスをトレースしているかに見える。しかし、そうではないように思う。
インタビューでは『マイルスやコルトレーンばかりじゃなく、自分たちのジャズをもっと聴いてもらえるようにしたい』と語っているが、そこにはマイルスのような自己存在を思想的に音楽に投影するというギリギリ感がなく、むしろとてもマーケティング的なのだ。ハンコックをカバーし、ボーカルを導入したヒップホップでカオスを生み出しつつ、ロックのニルヴァーナの名曲『Smells Like Teen Spirit』をカバーしながら、コルトレーンの『Love Supreme』もステージで演奏してジャズの継承性にもコミットする。そんなところにもインターネットの水平性を感じるのである。
『Black Radio』は、全編がヒップホップのスピリットに満ちあふれていてボーカルも多用されているが、コモンなどの<純正>ヒップホップと同じかと言えばそうではなく、やはりジャズなのだ。ジャズの要素を取り入れたヒップホップは沢山あるが、ロバート・グラスパーはヒップホップの要素をジャズに取り込んだと言えるだろう。
彼の音楽が、これからどうなっていくのか。それは誰にもわからない。ただ、今ジャズはここにいる、という時代性を感じるのである。
ロバート・グラスパーがそのような壮大な使命感を放出しているわけではないが、彼が生み出す音楽は、ブラックミュージックの一つの到達点である。
ミシシッピのデルタ地帯。フィールドハラーから始まったブラックミュージックは、ブルース、ゴスペル、ジャズ、ソウルと大きな流れを生み出しながら、ヒップホップへとたどり着いた。それら全てが水平化した現在、全てのブラックミュージックはひとつになろうとしているかのようだ。
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
