
大橋 郁がお届けする『KIND OF JAZZ』。
うろたえず、媚びない。
そんなジャズにこだわる放浪派へ。
主流に背を向けたジャズセレクションをどうぞ。
大橋 郁
松井三思呂
吉田輝之
平田憲彦
![]()
チャーリー・パーカー
撰者:平田憲彦

【Amazon のCD情報】
今ここに読まれようとしているテキストは、あらかじめ遊戯を回避しているかのようなあとがきに似た余録である。決して少ないとは言えないほどの引用が交錯しているが、それはなによりチャーリー・パーカーの音楽そのものが不意打ちのような引用に満ちているからに他ならず、まるで言語でパーカーに近づくことを企んだ無謀な試みと言えなくもない。
ジャズがスウィングからモダンへと変容する導火線を引いたパーカーの、ほんのわずかな数年間がなぜこのように70年以上も生々しい音楽体験としてとらえられているのか。なぜ1950年前後からこの21世紀に至る今でも多くのジャズメンがパーカーの音楽を学び、模倣し、まるでパーカーを体現しようとしているかのような時間を生きているのか。であるにもかかわらず、なぜパーカーは一般的にジャズファンに聴かれることが驚くほど少ないのか。
それを謎という一言で片付けてしまうことはたやすい。
しかし、図らずもこうやってその絡まった糸をゆっくりほどいていくうちに、余録は書き進められてしまった次第である。
パーカーの推薦音源は下のリストにまとめられているので、そちらを参照していただくとして、数え切れないくらいのミュージシャンに模倣されることが圧倒的に多いパーカーのサウンドが、ジャズファンやジャズバー、ジャズ喫茶で聴かれることが極端に少ないというその転倒と輪郭を、投影させてみることにする。
※
パーカー的なるものの誘惑
誰もがパーカーを知っている。ある種のビート、ある種のフレーズ、ある種のメロディに接して、人は思わず『パーカー的だ』とつぶやく。その気軽な断定は、絶えずパーカーを意識しているわけではない人間さえをも、容易に納得させてしまう。なるほど、これはまったくパーカー的と言うほかない状況だ。
しかしどういうわけか、そこで鳴り響いているサウンドがパーカーその人ではなく、あくまでもパーカー的なるものであり、いつまでたってもパーカーそのものが流れることはない。流れ続けるのは常にパーカー的サウンドなのだ。
いったいパーカーはどこへ消えたのだろう。コンファメーション、ナウズ・ザ・タイム、ムース・ザ・ムーチェ、リラクシン・アット・カマリロ、今もどこかのジャズバーやジャズ喫茶で流れ続けるパーカーのナンバーは、つねにパーカー的なるサウンドであり、パーカーそのものではない。
チャーリー・パーカーはまるで幻影のように、いまもジャズの暗喩であり続ける。ハードバップという光を照らされたジャズには、つねにチャーリー・パーカーという影がついて回る。それは悲しむべき足かせではなく、むしろ幸福な呪縛であるとさえ言える。
パーカーの楽曲は高度な演奏力を必要とし、誰もが容易に演奏できるというわけではない。そのサウンドを演奏する時、人はパーカー的に演奏しなければパーカーの楽曲の良さを表出できないことを知っている。あのビート、あのリズム、あのメロディを演奏しなければならない。テンポを変えたり、メロディにアレンジを加えたりすることがまるで禁忌であるかのように、パーカーを演奏する奏者は、パーカーのオリジナルサウンドに忠実であろうとする。
パーカーを演奏できることは、演奏力が優れていることの証であり、パーカーのナンバーが持つリズム、グルーヴを会得していることの具現化であり、ひいてはあらゆるジャズを演奏できる実力を有することを身を持って掲げているかのようだ。
人がパーカーを演奏するその時、奏者はパーカーそのものになる。その喜びが、パーカー的なるサウンドから伝わってくる勢いと情熱の正体なのだ。パーカー的なるサウンドがなぜあれほどの高揚感を表出しているのかは、奏者の達成感とパーカーとの一体感がサウンドに具現化されているからであり、そのような楽曲はパーカーを置いて他になく、米国の音楽史においてパーカーが特別視される所以である。
そして人は、そんなパーカー的サウンドを聴く。それはパーカーではない。しかしそれは、パーカーを幻影としながらもパーカーになりきろうという情熱を聴いていることにほかならない。まるでパーカー的なる奏者が媒介となって、パーカーそのものと、パーカーを聴かない人々をつなげているかのようだ。
アドリブという名のリズム
パーカーはこう言っている。
『音楽は基本的に、メロディ、ハーモニー、そしてリズムだ』
これはパーカーを理解するためのフックとなるコトバだが、あまりにも当たり前すぎてわかりにくい。しかし、パーカー的なるものではなくパーカーそのものを聴けば、その言わんとするところはたちどころに腑に落ちる。パーカーは、音楽に大切なものは『メロディとハーモニーが生きたリズム』、つまり、メロディとハーモニーがリズムそのものと一体化していることが大切だと言っているのだ。
パーカーの演奏がもっともイマジネーションにあふれ、クリエイティビティが発揮された時期は、サヴォイとダイアルで録音していた頃だが、そこで生み出され、録音された楽曲を聴くとよくわかる。パーカーが吹くアルトサックスのフレーズは、メロディがリズムそのものになっている。逆に言えば、リズムにメロディが内包されている、と言い換えることもできる。
これは、パーカーのクインテットのなかでもパーカーのみが成し得ている。ディジー・ガレスピーもそのような演奏をしているが、やはりパーカーの演奏が『メロディとハーモニーが内包されたリズム』という意味で抜きん出ている。その他のメンバーには、マイルス・デイヴィスも含め、パーカーのようなグルーヴは感じられない。パーカーのみが特異な存在感で突出している。
マイルスは、パーカーがカマリロ病院から出てきたあとのことを、次のように自伝で回想している。
『バードの創造性と音楽的アイデアには限りがなかった。いくらでもいろんなスタイルでやれたし、同じアイデアを繰り返すなんてこともなかった。彼は毎晩、リズムセクションを大慌てさせた。』
あまりにもイマジネーションがずば抜けていたため、演奏中にどんどんアドリブが飛躍してリズムセクションが付いていけない状況に陥ることが多かったという。しかし、ディジー・ガレスピーだけは違っていたようだ。
『バードと対等に渡り合えたのは、たぶんディズ一人だけだったろう。』
パーカーの想像力あふれるアドリブに対して、リズム隊はどうだったか。
『バードが彼の方法で素晴らしいソロをやりはじめたら、リズムセクションにできることは、ひたすらビートをキープしてストレートに演奏することだけだった。そして最終的には、バードはきちっと正しく、元どおりのリズムに合わせて戻ってくるんだ。いつだって、まるで頭の中で準備が整っていたような見事さだった』
※
メロディの即興演奏のことをアドリブというが、パーカーのアドリブが驚異的なのは、自身が語っているとおり、メロディにリズムが一体化しているからである。魅力的なアドリブという意味では、パーカーに限らず多くのジャズミュージシャンがそれを成し遂げているが、パーカーのアドリブにはリズムが徹底して張りついている。そこが、パーカーをパーカーたらしめている要因だ。
それが最大限に発揮されているのが、パーカーのオリジナル楽曲なのである。テーマ部分からすでに、メロディに強く張り付くリズムで構成されている。そのことでアドリブ部分での演奏がさらに自由度を増し、曲全体を通じて『メロディとハーモニーが内包されたリズム』が体現されるからこそ、パーカーの楽曲は演奏者を引きつけてやまない。
今もパーカー的なる演奏として好んで選ばれているパーカーの楽曲は、メロディとハーモニーが生きたリズムで作られているナンバーばかりだ。テーマ部分にはディフォルメされたシンコペーションがメロディと一枚岩のように一体化している。それは限りなくシンプルだ。しかし、コントラストのきついシンコペーションが加えられて上昇と下降を激しく繰り返すメロディは演奏者の実力を選別してしまうくらいの難易度で構成されている。それが、コンファメーション、ムース・ザ・ムーチェ、リラクシン・アット・カマリロといったハイテンポのナンバーなのである。
パーカーのオリジナル作品は、パーカーの考える音楽の本質が具現化しているからこそ演奏者にとってはパーカーを体現できる最適な楽曲なのだ。パーカー的なるサウンドを追い求める奏者がパーカーのオリジナル楽曲を好んで取り上げるのは、まさに自然な成り行きといえる。
さらに、ミディアムテンポ、スローテンポのナンバーに於いても、パーカーの考える『メロディとハーモニーが内包されたリズム』はしっかりと具現化されていることをパーカー的なる演奏者は知っている。ナウズ・ザ・タイム、ビリーズ・バウンスであり、クールブルース、パーカーズ・ムードといったナンバーは今も多くのパーカー的なる奏者を引きつけてやまない。
アート・ブレイキーの素晴らしいアルバム『バードランドの夜』をはじめ、ソニー・スティット、ジャッキー・マクリーン、フィル・ウッズ、ルー・ドナルドソン、あのコルトレーンも、さらにはアルバート・アイラー、サックス以外でもウィントン・マルサリス、ハンク・ジョーンズ、トミー・フラナガン、もちろん日本が誇る渡辺貞夫、果ては1986年生まれの新鋭、矢野沙織に至るまで、挙げていけばきりがないほどパーカーの楽曲は延々と取り上げられ続け、パーカー的なるサウンドは日常的にジャズシーンを彩っていると言っていい。
そこで鳴っているサウンドは、いかにもパーカー的だ。なるほど、これはパーカーだ、と言って手を打つ。よくぞここまでパーカーを演奏できたと聴き手は賞賛を送るのだ。そして同時に、これがパーカーそのものではなくパーカー的なるものであることに安堵する。それは、聴き手がパーカーそのものから感じるある種の距離感を、このパーカー的なるサウンドが埋めてくれているからにほかならない。
聴き手はパーカー的なるサウンドを聴くことでパーカーの音楽を共有出来るという、まるで疑似体験のような奇妙な状況に身を置く。
それは例えば、極上のシングルモルトウィスキーを水割りで飲むように、深く濃いフレンチロースト珈琲に砂糖とミルクを入れるように、本物をストレートで味わうにはキツすぎるという人が本物を味わえる有効な方法に似ている。
人はパーカー的なるサウンドは聴いて楽しめるのに、なぜパーカーそのものは聴けないのだろう。パーカー的なるサウンドを通じてパーカーを聴いているということは、わかる人にはわかっているのだ。しかし人は素知らぬそぶりでパーカー的なサウンドを聴き、聴いているのはパーカーではないという身振りをする。
同じことがレスター・ヤングにもいえる。パーカーはある意味でレスター的だ。レスター・ヤングはパーカーサウンドの根幹であるからこそ、レスターを聴くことはパーカー的なる何ものかを理解する手助けともなる。
対象化されるレスター・ヤング
チャーリー・パーカーの背後には、レスター・ヤングがいる。
フレッチャー・ヘンダーソン楽団でコールマン・ホーキンス風の演奏を強いられて自分らしさを発揮できず退団することになったレスター・ヤングは、1936年に古巣であるカウント・ベイシー楽団に復帰する。ここから1940年まで、ベイシーの黄金時代はレスターの黄金時代と同期する。
同じ1936年、ピアニストであるジェイ・マクシャンは自身の楽団を結成し、カンザスシティで活動を始める。
この年は奇妙な年だ。レスターがベイシー楽団に復帰し、マクシャンが楽団を設立、そして16歳のチャーリー・パーカーはまだまったく無名の存在で、セッションに明け暮れていた。
ベーシストのジーン・ラミーはパーカーを14歳の頃から知っている数少ない人物の一人だ。ラミーはこう回想する。
『ある夜、ベイシーとジャムっていたときのことだ。チャーリーはまったく合わせられなかった。ジョー・ジョーンズはバードがソロを始めると、突然、バードに対する彼の感情を示すために、シンバルをダンスフロアめがけて投げつけた。鼓膜が破れるかと思うような音をたてて落ちた。屈辱的な思いをしたパーカーは、楽器をしまい込むとその場を去った。ジョー・ジョーンズは出場者であるパーカーにゴングを鳴らしたんだ。』
当時はこのように、セッションで応酬し腕を競いながら上達していく環境が盛んであった。そこには、下手な演奏者に対する容赦ない罵声が飛び、ダメ出しのゴングが鳴らされるリングのような厳しさがあった。
『バードは俺のところに来てこう言った。今に見ていろよ!あいつらは俺にゴングをならした、今に見ていろよ!』
その場にレスター・ヤングはいたのだろうか。そのことを示す誰のコメントも残されていないが、16歳のパーカーが果敢にもベイシー楽団にジャムセッションを申し出て参加していたという事実はとても興味深い。酷評され、まるでつまみ出されたかのような扱いを受けたことも。
しかし、それでもパーカーのアイドルはレスターであり続けた。
ジーン・ラミーは、パーカーが17歳だった1937年に驚くべき変貌を遂げたことを、こう語っている。
『1937年の夏、バードの音楽は劇的に変わった。歌手のジョージ・リーが率いる小さなバンドで仕事をした。オザーク山地の田舎のリゾートで演奏していた。チャーリーはレスター・ヤングのソロの入ったカウント・ベイシーのレコードを全部持っていって、レスター・ヤングのフレーズを一音余さずに研究した。戻ってきたときには、カンザスシティで一番人気のあるミュージシャンになっていた。ほんの2、3ヶ月しか経っていなかったが、その変化は信じられないくらいだった』
オザーク山地から戻ってきたチャーリー・パーカーは、1938年にジェイ・マクシャン楽団に参加する。そして1940年、パーカーは初めてのレコーディングをマクシャン楽団で体験することになる。
1940年11月に9人編成のジェイ・マクシャン・オーケストラのメンバーとしてカンザス州ウィチタのラジオ局で録音された『アイ・ファウンド・ア・ニュー・ベイビー』が公式録音として最も古い記録である。ジェイ・マクシャン・オーケストラ時代の演奏は今も聴くことができる。マクシャン楽団でのパーカーのサックス演奏は流れるようなブロウがレスターによく似た印象だが、すでにその後のスピード感あるシンコペーションが含まれていることに気が付く。ニューオリンズの香りを強く残しながらも、ベイシーのスウィング感を存分に発揮したマクシャン楽団のサウンドは素晴らしいが、時折ベイシー風に弾くマクシャンと、レスターのフィーリングを強く醸し出すパーカーのサックスで、このバンドはとてもベイシー楽団に似ている。
ここでのパーカーは、まるでレスター的サウンドといっていいかもしれない。
しかし、パーカーは言っている。
『レスターに夢中になった。だが、レスターの影響を受けたわけではなかった。アイデアの方向性が全く違っていた』
パーカーは決して強がりで言っているのではない。1946年に行われたJATPのジャムセッションで、『レディ・ビー・グッド』をレスターとセッションしているパーカーの、その2人のサウンドを聴けば明らかだし、さらには、レスターの音楽のその後を聴けば分かり易いだろう。
あくまでも流れるようなスウィング・ブロウを美しく奏でるレスターに対し、パーカーはレスターの印象を残しながらもシンコペーションが効いたリズムで急速なアドリブをブロウする。
幾度となくコピーし、繰り返し練習して身につけたレスターの奏法を消化したパーカーは、自分ならこう演奏する、というイマジネーションが沸くまでに進化していたことが、1939年の自身の回想で理解できる。
『7番街のチリハウスでジャムセッションしていた。俺はこのとき、使っていたチェンジに飽きていた。何か他の方法があると思っていた。何かは聞こえていたけれど、それを演奏することはできなかった。とにかく、俺はその時「チェロキー」を演奏していた。そうしたら、コードの高い方の音をメロディラインとして使って、それをふさわしいコードチェンジに戻すことを発見したんだ。それまで聞こえていたものを演奏できたんだ、俺は生き返ったよ』
ジェイ・マクシャン楽団を離れたパーカーはニューヨークへ向かい、そこでディジー・ガレスピーに出会い、自身のバンドを結成、マイルス・デイヴィスを採用、そしてサヴォイ、ダイアルへの録音といった風に、黄金時代を迎えるのである。
レスター・ヤングに憧れた少年は、やがてレスターを消化して自身のイマジネーションを具現化する方法を発見し、ジャズの転換点とも言えるビバップを創造していく。
レスターがジャズのスウィング時代を頂点に導いたように、スウィングを大きく前進させてリズムを強化し、アドリブのクリエイティビティを拡張させていく。
1953年に行われたジョン・フィッチによるインタビューで、パーカーはこう語っている。
パーカー: 俺はバイダーベック的な音楽にはあまり詳しくないんだよ。ただ、今の革新的音楽、ビバップと呼ばれているものだけど、それはバッハやブラームス、ベートーベン、ショパン、ドビュッシー、ショコターヴィッチ、ストラヴィンスキーなどの俺たちの先駆者たちにインスパイアされたものでなければ、影響を受けたというわけでもないんだ。
フィッチ: 誰が重要なミュージシャンなのかな、もちろん君も加えて。誰がそれまでの音楽に満足できなくて、実験を始めたんだい?
パーカー: ああ、ちょっと訂正させてくれないかな。俺たちがそれまでの音楽に不満を持ってたわけじゃない。違うコンセプトが見えたんだよ。それが、俺たちが向かうべき方向だって感じたんだ。それは1938年に始まった。遅くとも1945年よりも前だよ。ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンク、ケニー・クラーク、チャーリー・クリスチャンもいたね。1937年には、バド・パウエルも、ドン・バイアスも、ベン・ウェブスターもいた。
※
パーカーを夢中にさせたレスターは、ベイシー楽団在籍の前はフレッチャー・ヘンダーソン楽団にいたが、フレッチャー・ヘンダーソンは1939年にベニー・グッドマンと合流する。コールマン・ホーキンスもフレッチャー・ヘンダーソン楽団に在籍し、同じく同僚だったルイ・アームストロングに強い影響を受ける。
そのサッチモはもともとキング・オリバー楽団出身。オリバーはもちろん、ニューオリンズジャズの創始者と言っていいコルネット奏者だ。
そう考えると、キング・オリバーから、フレッチャー・ヘンダーソン、サッチモ、コールマン・ホーキンス、ベニー・グッドマン、カウント・ベイシー、そしてレスター・ヤングは互いに影響を与え合った者同士であり、音楽性としても一直線上につながっていることがわかる。
その直線は、チャーリー・パーカーにたどり着く。
パーカーのサウンドがどれほど急速テンポのアドリブが展開されていようとも、どこかに明るさとスウィングを感じられるのはそのためである。
パーカーはレスターの楽曲の中でも『レスター・リープス・イン』を好んで演奏したが、オリジナルのレスターのバージョンに比べて驚くほどリズム感が強化され、アドリブも超高速で演奏された録音が残されている(1952年、ロックランド・パレスでのライブ)。
パーカーの言葉、カバーしたレスターの楽曲、そしてオリジナルナンバーに、パーカーが思い描いた音楽の姿が見事に投影され、具現化されている。
パーカーは、モダンジャズを創設したと言われているが、むしろ、スウィングジャズにケリを付けた、と言った方がいいのかもしれない。
ジャズを拡張するということ
キング・オリバーのデキシーランドに端を発するジャズのサウンドは、サッチモ、コールマン・ホーキンスを経てレスター・ヤングに引き継がれ、パーカーがアドリブを極限にまで発展させた。しかし、そのパーカーのサウンドは誰が引き継いだのだろう。
マイルスだろうか。あるいはコルトレーン、もしくはアイラーなのだろうか。
歴史的にみても、あらゆる表現の原初は生活に根付いた必然的なものだった。絵画は、そもそもは説明図であり、伝達の手段だった。音楽も、そもそもは生活の中の余興や娯楽であり、祭事の素材の一つであった。しかし、人類の生活が発展していくと共に生活に必要とされていた絵画や音楽はやがて文化と呼ばれる『鑑賞の対象』、つまり『芸術』という付加価値をもつ存在へと変化していく。もともと飲料を入れて飲むために作られたに過ぎない器が、いつのまにか『使うのではなく眺める』ものとして変化し、場合によっては投機の対象となったり資産価値を持つ財産となったりと、本来の目的から大きく逸脱していったような変化である。
レスター・ヤングの時代までは、ジャズはダンスミュージックであり、人を踊らせて演奏料をもらう仕事であった。そこには、キング・オリバーから継がれてきた『芸能』という側面が色濃く残っていたし、レスターまでのジャズはその要素で成立していた。この流れにケリを付け、ジャズという音楽に『踊る』以外の要素を導入したのが、チャーリー・パーカーなのである。
『踊る』以外の要素、それは『演奏者の表現思想(コンセプト)』と言い換えることが出来る。先のインタビューでも語られているが、ジャズにコンセプトという考え方を見いだした最初のミュージシャンがパーカーだった。
パーカーはさらにこう語っている。『デキシーランドは好きだが、古代の音楽だ』と。自分がデキシーを上手く演奏できるとは思わないし、そうするつもりもないと。パーカーには、自分のアタマに鳴り響くサウンドを具現化していくという強いパッションがあった。そこには、自分の音楽で人を踊らせるという発想などみじんもないのだ。イマジネーションをサウンドにしていくという発想。観客のためではなく自分のために音楽をやっていたのである。だからこそ、パーカーのサウンドにまず飛びついたのが、同じミュージシャンであったのだ。今でもパーカーが『ミュージシャンズ・ミュージシャン(音楽家のための音楽家)』と言われるゆえんだ。
これこそ、パーカーがジャズの歴史で果たした最大の役割なのである。
『パーカー的なるサウンド』が今も、この21世紀にも演奏者に好まれるのは、まさにこれが理由である。パーカーの音楽は、楽譜やメロディが魅力的であるだけでなく、演奏する奏者が自分の想像力を対象化し、自分の演奏力を客観化しつつも自己との対話として演奏できる音楽なのである。しかもそこには、デキシーから脈々と流れるスウィングフィーリングも、米国音楽の中心軸であるブルースフィーリングもたたえている。
インタビューでも語っているとおり、パーカーは何かの具体的な音楽に影響を受けたというのではなく、『音楽を、観客を楽しませるめの道具から、自己を表現するための手段』に拡張させた、ジャズの最初のミュージシャンだったといえる。別の言い方をすれば、『娯楽音楽だったジャズに芸術性を付加させた』ということである。きっかけはあくまでもレスター・ヤングだったが、パーカーはレスターになりたかったわけではないのだ。
パーカーに『俺の心臓の半分』とまで言わせたディジー・ガレスピーも、そういった表現指向を持っていたが、ガレスピーにはまだ『芸能としてのジャズ』というDNAが色濃く残っていた。『ソルト・ピーナッツ』のスキャットは、ガレスピーがまだ芸能ジャズを生きていた証しでもある。
サッチモにもそういう『芸能としてのジャズ』という側面が濃厚で、それは生涯続いている。それがサッチモの音楽をなんら貶めているものではないが、マイルスなどは、サッチモやガレスピーのそういう『芸能性を』嫌悪している。ここにもひとつのヒントがある。
もちろん、パーカーひとりがジャズを表現手段としての音楽に拡張させたわけではないのは言うまでもない。前述のとおり、パーカー本人が語っているように、パウエル、モンク、ガレスピーなど、同時代のミュージシャンとのセッションを通じ、パーカーが牽引役となっていったということである。
パーカーが登場するまで、ジャズはあくまでも『娯楽芸能(Entertainment)』という存在理由で音楽が鳴っていた。しかし、パーカーがそれを『表現芸術(Art)』の領域へと拡張させた。そのバンドにいたマイルスが、パーカーの表現指向に強く影響を受けたのである。
マイルスはパーカーの元を離れてから、自分のバンドで『ムース・ザ・ムーチェ』や『ナウズ・ザ・タイム』を演奏したことはない。しかし、マイルスはパーカーが確立した『表現手段としてのジャズ』を本質的な意味で受け継ぎ、発展させていったといえる。その最初の作品が、1949年に録音された『クールの誕生』である。
※
パーカーが革新的に演奏していた究極のアドリブ演奏は、少なくとも観客が踊れるような音楽ではなく、多くのミュージシャンが同じように演奏できるというような生やさしいレベルでもなく、難易度も表現レベルも極めて高い音楽になっていた。
そんな状況の中で、分かり易いメロディと、ミディアムテンポで親しみやすく、落ち着いて聴ける音楽をバンドアンサンブルでつくり出したのが、マイルスの『クールの誕生』だった。
マイルスは自伝でこう言っている。
『「クールの誕生」はオレが思うに、バードとディズの音楽に対する反動として支持され、コレクターズ・アイテムになったみたいだ。バードとディズは、ヒップでやたら速い音楽をやっていたが、よほどのわかり良い奴じゃないと、音楽のユーモアとかフィーリングはつかめなかった。スイートじゃなかったし、ガール・フレンドとキスしようとして口ずさめるような、和声的なメロディーも持ってなかった。ビバップには、デューク・エリントンのような人間性もなかった。誰にでも簡単に見分けられるような要素が、まるでなかった。バードとディズは偉大だし、すばらしいし、意欲をそそられるものではあったが、決してスイートじゃなかった。その点「クールの誕生」は、ちゃんと聴けるし、口ずさみもできたから、ビバップとはかなり違っていた』
1949年は、パーカーのダイアル〜サヴォイと連なる黄金時代が一区切り付いた年であり、マイルスがパーカーの元を離れて独り立ちを始めようとしていた年でもある。そしてパーカー自身の表現指向が、ヨーロッパのクラシック音楽へと興味の対象をシフトし始めた年でもある。
1949年3月以降、パーカーのクインテットに新曲が加わることがなくなる。毎晩同じ曲を演奏することで、やがてメンバーに停滞意識が生まれてしまう。パーカーのアドリブも同じことの繰り返しが増えていく。手持ちのフレーズが増えていくわけである。これは、イマジネーションの枯渇と言うよりはむしろ、あらゆるアドリブ演奏を突き詰めた結果、表現をするための土台がアドリブではなく作曲へと移行しようとしていた現れと言える。アドリブは感覚的な即興の作曲だが、クラシック的楽曲の作曲は、即興ではなく音を構築していく理論的な創作活動と言える。パーカーは、アドリブから別の創作活動へと方向転換し始めようとしていた。
かつてマイルスに『楽譜なんか捨ててしまえ』と言ってイマジネーションをなによりも重視したパーカーは、徐々に音楽的興味をシフトしていたのだ。その対象は、ヨーロッパのクラシック音楽である。
1948年のインタビューで、パーカーはクラシック音楽から受けた感動を語っている。シェーンベルク、ドビュッシー、ストラヴィンスキー、ショコターヴィッチ、ベートーベン、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、ヒンデミット、ラヴェル、ワーグナー、バッハの楽曲への感動を熱くストレートに語っているのである。ここで注目すべき作曲家は、言うまでも無くシェーンベルクやヒンデミットという現代音楽に通じる作曲家だろう。音楽に抽象性や空間性を見いだしていたことを物語るコメントであり、パーカーにとって音楽とは、観客のための娯楽演芸ではなく、あくまでも自己表現の手段であったことが改めて理解できる。
パーカーは近い将来、フランスの音楽アカデミーに通ってクラシック音楽と作曲を学ぶことを真剣に考えていた。米国で演奏して経済面を充実させ、フランスで作曲の探求とプライベートな休息を得るというライフプランであった。この計画はパーカーの死によって実現しなかったが、晩年のパーカーの音楽を知る上で大きなヒントとなるエピソードだ。
4人目にして最後の妻であるチャンに、パーカーはこう語っていたという。
『音楽が違って聞こえる。会話のように聞こえるんだ』
アドリブ演奏を限界点まで突き詰めた結果、自分の演奏を『対話としての音楽』ととらえるように変化していた。
似た話がチャーリー・ミンガスの発言からもうかがえる。
『俺たち(パーカーとミンガス)は長い間セットの間にあらゆることについて話し合ったものだ。結論がで出ないうちに、またステージに戻らなければならなかった。彼はよくこう言っていたよ。「ミンガス、続きはステージでやるぞ。俺たちは楽器でこれを話し合おう」』
もう一度、パーカーの言葉を思い出したい。
『音楽は基本的に、メロディ、ハーモニー、そしてリズムだ。』
この言葉には、実は続きがある。
『でも、音楽でそれ以上のことができるのではないかと思う。どんなやり方でも、見事に描写できるはずだ』
パーカーが考えていたこと、やろうとしていたことのすべてが、この言葉に込められている。
パーカーを継ぐもの
チャーリー・パーカーは、音楽を演奏しながら客を踊らせることよりは、自身のコンセプトをサウンドに具現化することに熱中したミュージシャンだった。そのコンセプトとは、メロディとハーモニーがリズムに一体化することであり、音楽を表現として高めて行くことであり、サウンドで対話することであった。
それが、当初はアドリブという即興演奏の土台を生かして徹底的に追及し、やり尽くした後には西洋音楽の作曲という土台で新たな展開を目指そうとした。
ジャズのアドリブを極限まで追求して自己の表現を具現化できたからこそ、その後のミュージシャンはパーカーの楽曲を演奏してパーカー的なるサウンドを模倣することで、パーカーが指向したコンセプチャルなサウンドクリエイションを共有できている。
パーカーのサウンドは、演奏者の魂に火をつけるのだ。逆に、演奏や表現活動をしない聴衆にはわかりにくい表現になる場合が少なくない。
音楽や絵画、演劇や文学などの『表現』は、娯楽として大衆に楽しまれているうちは身近な存在として愛されるが、そのクリエイティビティ面が芸術表現へと向かえば向かうほど大衆から離れていく。そして、革新的な芸術表現を達成することと引き替えに、同じ世界の表現者には強く支持され、表現をする側ではない大衆には背を向けられるのである。
マイルス・デイヴィスが音楽表現者として類い希な天才であるのは、音楽に存する芸術表現の追求をパーカーから学んで具現化して継続しただけでなく、大衆性を忘れなかったところにある。それはトレンドであったりファッションであったり、マイルスの言うところの『ヒップ』な要素であり、また『ポップ』な要素でもあった。『ペーパームーン』や『白雪姫』、またマイケル・ジャクソンの楽曲を取り上げつつヒップなアレンジを導入するセンス。ファンクやロック、ヒップホップという音楽のムーブメントを積極的に取り入れていく同時代性、その大衆感覚が、マイルスが持ち得た才能である。
マイルスは1949年に『クールの誕生』を録音して難解なビバップから距離を置きつつジャズを大衆に引き戻した。1954年には『ウォーキン』を発表してファッショナブルでキャッチーなファンキー・ブルースを世に送り出し、その後のジャズを圧倒的にリードしていく存在となる。
『ウォーキン』は、ブルースとファンクをミディアムテンポにアレンジし、ビバップを分かり易くサウンドに取り入れることで、黒人音楽の継続性とダンスミュージックの大衆性をジャズに取り戻した作品として、画期的なレコードだった。しかも、スウィング時代ではビッグバンドでしか生み出し得ないとさえ思われていたジャズのダンスグルーヴを、小編成のバンドで達成したことで、ジャズの表現形式を再定義したという重要な役割も果たしたと言える。『ウォーキン』以降、ジャズは多くても7人、通常は4人か5人のバンド編成がスタンダードフォーマットとなる。
その『ウォーキン』が生まれた1954年といえば、パーカーが『プレイズ・コール・ポーター』を録音した年だ。究極のアドリブ演奏を突き詰めてやり尽くしたパーカーが、ビッグバンドやストリングスとのセッションを試しながら、次なるステージへ関心を向けていた時期の最後の小編成録音であり、そして、パーカーの生涯最後となるスタジオ録音でもあった。
『プレイズ・コール・ポーター』でのパーカーのブロウは、もはやアドリブを追求する表現者というサウンドではない。パーカーが重視したメロディとハーモニーとリズムの一体感がほとんどなく、イマジネーションあふれるアドリブは姿を隠している。
この録音は、今までは『酒とドラッグでボロボロになったパーカーが、ひらめきが鈍ったアドリブしか演奏出来ない惨めな姿をさらした作品』との見方が多勢を占めていた。しかし、パーカーの言葉と演奏の変遷をたどっていけば、『プレイズ・コール・ポーター』が悲惨な失敗作ではないことは明らかだ。この作品は、アドリブを突き詰めたパーカーが次へのステップへの足がかりとする分水嶺としてある。
つまり、1960年代後半のマイルスが4ビートジャズから8ビートとファンクへ方法論が移行していったように、1954年のパーカーにとって興味関心の矛先が西洋音楽的作曲へとシフトし、アドリブでの即興作曲ではなくなっていた、ということであると解釈出来る。その分岐点的な作品が、『プレイズ・コール・ポーター』である。
しかしそうは言っても、マイルスの『ウォーキン』とパーカーの『プレイズ・コール・ポーター』を同時代の音ととして聴けば、1954年とは、パーカーとマイルスがその音楽的リーダーシップを知らず知らずのうちにバトンタッチした年だと思わずにはいられないことも、歴然とした事だろう。
パーカーは、ミュージシャンとしてクリエイティビティや芸術性という面がずば抜けていて、マイルスのようなポップでヒップな大衆性が薄かった。それがために、当時から現在に至るまで、演奏者や表現者には強烈にリスペクトされながらも、大衆に聴かれることが少ないのである。
パーカーがジャズのみならず音楽の歴史に重要人物として記憶されているのは、パーカーが生涯にわたって追求した音楽芸術表現追求の姿勢と、その成果がビバップ、リズム、アドリブという圧倒的サウンドとして屹立し、評価されているからだ。しかし、それが多くの一般的な聴き手である大衆の支持を得るかと言えば、それは別問題である。
パーカー的なるサウンドは、今日も世界中のどこかで流れている。それはパーカーではない。しかし、パーカーが目指したサウンドが徹底して表現指向であり、そのサウンドが音楽を追求する本質的な芸術であったために、いつの時代でも存在する表現指向のミュージシャンを惹きつけてやまない。『パーカー的なるサウンド』を聴くことで、人はその音楽のみならず、パーカーが追求した芸術性をも聴いているのである。
ダ・ヴィンチやセザンヌ、デュシャン、バッハ、モーツアルト、シェイクスピアが、いつの時代も目標とされ、常に模倣されつつ新しい表現の土台となっている表現者のように、パーカーは常にそこにいる。
※
チャーリー・パーカーの音楽を引き継いだのは、誰だろう。
まずはマイルス・デイヴィスである。パーカーのバンドメンバーとして身近にいた事も要因だったのだろう、マイルスはパーカーの本質である芸術表現指向を正確に受け継ぎ、そこにパーカーには足らなかったポピュラリティを導入、ジャズの芸術性を高めながら大衆性をも拡大した。ビバップからヒップホップまでの広範囲な黒人音楽領域で活動したジャズミュージシャンは、100年を超えるジャズの歴史で、マイルス以外に見当たらない。
晩年のパーカーが指向していたクラシック音楽への接近という思考は、誰が引き継いだのだろう。実はこれもマイルスなのだ。マイルス自身はそれほどクラシック音楽への傾斜はなかったが、そのバンドメンバーだったジョン・コルトレーン、ハービー・ハンコック、チック・コリア、キース・ジャレットなど、彼らがクラシックや現代音楽に見られる抽象性や精神性をジャズに導入し、引き継いでいった。マイルスはパーカーから芸術的思考を受け継ぎ、ハブとなって拡散させたのである。
そして、もう一つ。パーカーの音楽を引き継いだ奏者がいる。
それは、紛れもなく『パーカー的なるサウンド』を生み出す、すべての奏者なのだ。
彼らが本当の意味での、パーカーの後継者なのである。
だから、誰もがパーカーを知っている。ある種のビート、ある種のフレーズ、ある種のメロディに接して、人は思わず『パーカー的だ』とつぶやく。その気軽な断定は、絶えずパーカーを意識しているわけではない人間さえをも、容易に納得させてしまう。なるほど、これはまったくパーカー的と言うほかない状況だ。
※
チャーリー・パーカー 推薦アルバム
今回の推薦アルバムは、この一枚、というセレクトではなく、パーカーを聴くならこのあたりでどうだろう、というガイドである。パーカーは難しい、パーカーはわからない、パーカーは疲れる、みなさんそれぞれ一家言あるだろうが、それはそれとして、むしろパーカーを聴いてみたい、あるいは、昔聴いてよく分からなかったが、もう一度聴いてみようかな、という人々に捧げたいディスクガイドである。パーカーが大好き、とか、最高、とか、ジャズはパーカーがあれば充分、という人にとってはもの足らないセレクトであると思うので、ご容赦願いたい。

Bird Symbols
Charlie Parker
【Amazon のCD情報】
ダイアル録音のベスト盤。一言で表現するなら、人類の遺産。そうとしか言いようのないくらいのアルバム。ダイアル時代のみなので、サヴォイ録音の作品は当然入っていない。それはこの下で紹介するアルバムでどうぞ。この『Bird Symbols』はパーカーの3番目の妻、ドリス・パーカーが作ったレーベル、チャーリー・パーカー・レコードの作品として、また別の意味がある。マイルスがドリスを批判しようが、世間が何と言おうが、死んだ夫の作品からベスト作品を集めてレコードを作るなんてことをしてくれる妻は、歴史的にも世界中見渡してもほとんどいないだろう。ダイアル時代のベストテイク集は他に何枚も出ているし、このアルバムよりも音が良いアルバムもいっぱいある。しかし、それでもこのアルバムの価値は普遍である。もちろん内容が素晴らしいことは言うまでもないことだが、世の中には『特別なアルバム』というものがあるのも、また事実なのだ。
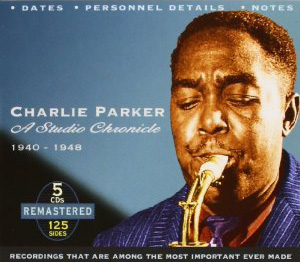
A Studio Chronicle 1940-1948
Charlie Parker
【Amazon のCD情報】
パーカーの全キャリアのうち、ヴァーヴ以外の時代をほぼカバーして、マスターテイクのみを集めたベスト盤のCD5枚組ボックスセット。抜群に音が良い。パーカーの音源は音が悪いと思っている人は、是非このリマスターを聴いてほしい。クリアなサウンドから聞こえてくる生々しいパーカーのきらめくようなアドリブに驚愕することと思う。この『A Studio Chronicle 1940-1948』は真の音楽的意味で人類の遺産と言い切れる。ものすごい演奏ばかり入っている。何かコメントすることすら気後れしてしまうくらいのエネルギーに満ちあふれた作品集。修業時代と言えるジェイ・マクシャン・オーケストラ時代も素晴らしい演奏であることに気がつくだろう。タイニー・グライムスのバンドに参加したときの演奏や、サラ・ヴォーンとの共演、ギター入りの珍しいトリオ演奏など、ビバップを極める前のパーカーだが、それでも演奏は突き抜けている貴重な録音も楽しめる。5枚組というボリュームだが、結果としてこのアルバムが最もコストパフォーマンスに優れた選択。とりあえず買っておいて、有名曲からじっくり聴くという方法もあるし、流しっぱなしにしてビバップの空気を浴びるのも良いし、パーカーの真髄がつまっているコレクションなので、『これがあれば大丈夫』的な、いわゆる『鉄板』アルバム。
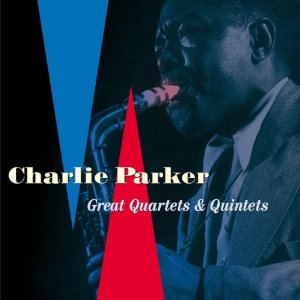
Great Quartets & Quintets
Charlie Parker
【Amazon のCD情報】
ジャケットは『Night & Day』の流用というかパクリなのでパチモンと思うかも知れないが、ご安心を。ヴァーヴ時代のコンボ演奏だけを、さらにマスターテイクのみを集めているので、潔く、しかも恐ろしくイキが良い。録音はサヴォイやダイアル時代に比べて抜群に良いので、聴きやすいことこの上ない。演奏内容はもちろん文句の付けようもない素晴らしさ。ハイライトはガレスピーとの再会セッション『Bird & Diz』の全曲収録だろう。ガレスピーとのコンビネーションはやっぱりすごいし、モンクはいつも通りのモンクで、パーカーとガレスピーの典型的ビバップのグルーヴとは違ったメロディとタイミングのピアノ。そんなユニークな調和が面白い。余談ながら、マイルスの素晴らしさも味わえる。
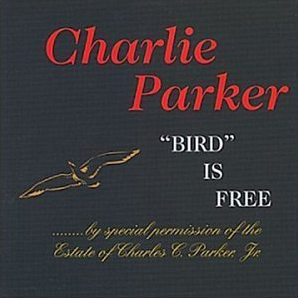
Bird Is Free
Charlie Parker
【Amazon のCD情報】
1952年、ニューヨークのロックランドパレスでのライブ。こんなに音が悪いのによく商品化しようと思ったものだが、決断した人々には拍手である。このライブはワンホーンで吹きまくる鬼気迫るパーカーを聴ける。悪すぎるサウンドの向こうから、忘我の境地でサックスを吹き狂うパーカーを感じることが出来るだろう。編成は、一部ストリングス入りのナンバーもあるが、全体的にはギター入りのクインテットなので、つまりワンホーン。ライブでのパーカーはスタジオ録音とひと味違って時間の制約を受けずに吹ける感性の解放を味わえる魅力がある。その中でも筆舌に尽くしがたい演奏が『レスター・リープス・イン』。これは史上最速バージョンと言われているが、あまりにも急速なアドリブながら、ただ早吹きなだけではなくビートも強烈で、しっかりとメロディが美しく演奏されているところが驚異的。この音の悪いアルバムはマニア向けであることは間違いないが、パーカーを好きな『わかる人』にとっては、まさに猫に鰹節なヤバイ一枚。そうでない人にとっては単なる雑音集かもしれないが。

At Storyville
Charlie Parker
【Amazon のCD情報】
ともかく総合的にバランスが良く聴きやすい1953年のライブ。最晩年の録音と言ってもいいが、それでもパーカーは33歳。バリバリである。ブルーノートがリリースするだけあって、サウンドのバランスも選曲も申し分ない。冒頭4曲のピアノはレッド・ガーランドで、ギター入りのクインテット、つまりパーカーのワンホーン。後半5曲はサー・チャールズ・トンプソンの職人ピアノ、ドラムはケニー・クラークというスゴイ面子。気持ちよく、また安心して聴ける。選曲も有名曲が多く、はじめてパーカーを聴く、という人にはこのアルバムを勧めることが多い。聴き易すぎて普通に聞こえてしまうが、やはりパーカーのアドリブはスゴイ。ともかくメロディが美しいのである。そうはいっても、飛ばしまくるパーカーではなく、比較的落ち着いてのんびりペースで演奏しているので、聴いているこちらもリラックスできる。語弊があるが、BGMにもなるパーカー、といえばわかりやすいかもしれない。

Diz N Bird at Carnegie Hall
Charlie Parker
【Amazon のCD情報】
パーカーとガレスピーのセッションは多くあるが、このライブ盤は白眉。1947年のカーネギーホールライブ。時代はパーカー全盛期でアドリブのひらめきは奇跡的な輝きに満ちている。掛け合いもスゴイが、なによりパーカーのほとばしるアドリブが空を駆け巡り、驚異的。スピード、メロディ、グルーヴ、それをとっても超一級。対するガレスピーの演奏も素晴らしい。サウンドのバランスは、わざとなのか、これが精一杯だったのかわからないが、パーカーとガレスピーの音が際だっていて、その他の楽器がやや後退気味。しかしパーカーを聴きたい我々としてはむしろ好都合。選曲も申し分ない。『コンファメーション』が入っているところが貴重。このライブは本当にスゴイ。ちなみに、パーカー入りのクインテットは冒頭の5曲のみ。あとはガレスピーのビッグバンド。しかし、その5曲のためだけでも買いのアルバム。太鼓判。

Complete Live at Birdland
Charlie Parker &
Dizzy Gillespie
【Amazon のCD情報】
バードランドというニューヨークのジャズクラブが、当時のジャズ界スーパースターだったチャーリー・パーカーにあやかって名付けられたのは有名な話だが、実際店内には巨大なパーカーの写真が飾られ、天井には鳥かごがいっぱいぶら下げられるなど、かなり本気度の高いパーカーリスペクトの箱だった。そこで頻繁に行われていたのがライブをラジオで放送する試みである。このアルバムはCBSがリリースした『Summit Meeting』の強烈な4曲を含む、パーカーとガレスピーのバードランド共演ライブのコンプリート。やはり、冒頭の4曲は空前の演奏といっていい。パーカーとガレスピー、そしてピアノはバド・パウエル。パウエルのピアノ、ドラムのロイ・ヘインズも良いが、なによりパーカーとガレスピーのアドリブが凄すぎる。1曲目から飛ばしまくり、キレまくりの二人は壮絶と表現してもいいくらいの、天に駆け上るかという鮮やかなアドリブを披露している。実際、演奏スピードも凄いが、それ以上に『スピード感』が圧倒的。そしてただ剛速球なだけではなく、アドリブのメロディラインが美しいことがポイント。想像力あふれるアドリブラインが美しいメロディを伴って高速に、またリズミックに演奏され、それがパーカーのアルトとガレスピーのラッパがめくるめく掛け合いとなって繰り広げられ、圧倒的で感動的な演奏を体感できる凄まじいアルバム。
=======
参考文献
『チャーリー・パーカー 〜モダン・ジャズを創った男〜』
カール・ウォイデック 著
岸本礼美 訳
水声社 刊
『完本 マイルス・デイヴィス自叙伝』
マイルス・デイヴィス、クインシー・トループ 著
中山康樹 訳
JICC出版局 刊
『監督 小津安二郎』
蓮實重彦 著
筑摩書房 刊
ウェブサイト
www.birdlives.co.uk
![]() Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
Copyright 2010- Banshodo, Written by Iku Ohashi, Sanshiro Matsui, Teruyuki Yoshida, Noriiko Hirata, All Rights Reserved.
